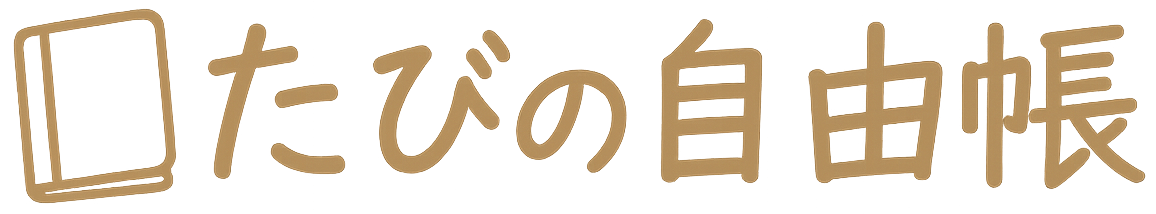エチオピアを旅していた2週間、私は現地の食文化にできるかぎり身を委ねようとしていた。
見慣れない主食インジェラ、儀式のように始まるコーヒーセレモニー、そして牛やヤギの生肉。どれもが新鮮で、深くて、時に強烈だった。
私は好き嫌いがほとんどない。海外でも現地の料理を受け入れることに、これまで大きな壁を感じたことはなかった。
けれど今回、食べ続けるという行為のなかで、気づかぬうちに疲れが蓄積していた。味の問題でも文化の問題でもない。
ただ、自分のリズムが少しずつ狂っていく感覚──それは、身体の奥から静かにやってきた。
文化に合わせることは、決して悪いことではない。
でも、どこかで「合わせすぎてしまうこと」もまた、旅の難しさなのかもしれない。
この記事では、エチオピアの食文化との出会いと、その中で私が見つけた「無理をしない関わり方」について書いていこうと思う。
毎食インジェラの現実

エチオピアの滞在中、私の食生活はインジェラ一色だった。
主食というより、すべての料理の土台であり、逃れようのない前提になっていた。
私は好き嫌いが少ない方だが、それでも「またか」と思うようになるまでに、そう時間はかからなかった。
発酵の主食、インジェラとは
インジェラは、テフという穀物を発酵させて焼き上げた、クレープ状の主食だ。
ふわふわと軽く、しっとりとした質感。そしてほんのりとした酸味がある。
一枚の大きな円盤の上に煮込みや野菜炒め、生肉などが盛られ、それらをちぎったインジェラで掬って食べる。
最初に食べたとき、私はそれなりに楽しんでいた。
見た目にも珍しく、味も悪くない。「これがエチオピアか」と思えたあの感覚は、今でもよく覚えている。
しかし、徐々に心境は変化していく。
日本で言うご飯やパンのような位置づけかもしれないが、インジェラはそれらのように中立的ではない。
味の個性が強い。毎日、毎食、ずっと同じ感覚が口に残る。
好き嫌いではなく、逃げ場がなかった
インジェラは朝・昼・晩、どこへ行っても、何を頼んでも出てきた。
たった数日で、その酸味と食感が身体にずっしりと蓄積していくのを感じ始めた。
私は基本的に、現地の食文化を受け入れることに抵抗はない。
インジェラも、決して嫌いではなかった。たまに食べるなら、むしろ好きな部類に入るかもしれない。
しかし、問題は「逃げ場がない」ことだった。
ふと気づくと、「またインジェラか」と思っている自分がいた。
これは飽きの問題ではない。選択肢のなさに、身体と心が音を上げていた。
文化に従おうとする自分と、それに疲れていく身体。
そのズレが、少しずつ積み重なっていった。
コーヒーセレモニーの心地よさ

エチオピア滞在中、もっとも自然に受け入れられた文化体験のひとつが、コーヒーセレモニーだった。
それは単なる一杯のコーヒーではなく、空間と時間を共有する儀式のようなものだった。
そして私はコーヒーが好きだ。その好みと文化がうまく重なったとき、抵抗なく馴染める感覚が確かにあった。
豆を煎るところから始まる時間
エチオピアでは、コーヒーは豆を煎るところから始まる。
生豆を炭火でゆっくり焙煎し、手で砕いて、金属のポットで煮出す。
この一連の流れを、目の前で見せながらゆっくり進めていくのがコーヒーセレモニーだ。
その間、特別な会話があるわけではない。けれど、その「待つ時間」こそが意味を持っているようだった。
湯気と香りが立ち上がる空間に身を置いていると、体も気持ちもほぐれていくようだった。
自然と馴染んだ体験
出てきたコーヒーは、想像以上にしっかりとした苦味があり、香りも力強かった。
一杯目は「歓迎」、二杯目は「交流」、三杯目は「祝福」。
現地の人がそう説明してくれたこの流れにも、どこか儀式的な重みがあった。
それでも私は、肩肘を張らずに飲んでいた。
無理をせずとも、自然とその場に溶け込めていた。
それは、コーヒーが好きという個人的な好みと、文化的なスタイルがうまく重なった瞬間だった。
コーヒーセレモニーのように自然と馴染めた体験もあった一方で、もうひとつ印象に残った食文化がある。
それが、生肉。
生肉を食べすぎた夜

エチオピアでは、生の牛肉やヤギ肉を食べる文化がある。
テレセガと呼ばれる生肉料理は、ごちそうのひとつとして親しまれている。
煮込みや焼き肉ではなく、生肉をそのまま食べるスタイルだ。
日本では生肉を食べる際には厳しいルールがあり、気軽に食べれるものではない。限られた肉の限られた部位のみ生で食べることができる。
エチオピアではコロコロステーキのような生肉が食べられる。そして味は最高だった。
それでも、私はこの食体験を通して、慣れや量、そして食文化との「距離感」のようなものを強く意識することになった。
本来は分け合う料理だった
テレセガは本来、家族や仲間と分け合って食べるものなのだろう。
けれど私は、そのことを知らなかった。
そして2晩連続で、1人で500gずつ、生の牛肉とヤギ肉を平らげてしまった。
1日目は牛肉。現地の唐辛子系のタレにつけて、辛味のある刺激的な味で食べた。
初めての体験ということもあり、正直、楽しかった。
2日目はヤギ肉。同じように食べ始めたものの、途中から唐辛子がきつく感じてきた。
そこで、塩とコショウをもらい、慣れた味付けに切り替えた。
それは無意識の「回帰」だったのかもしれない。
すでに私は、文化に向かう姿勢から、自分に戻る準備を始めていた。
好きでも、無理は続かない
その夜、腹痛に襲われた。
生肉が原因だったのか、それ以外の要素もあったのかはわからない。
ただ、翌日から2日ほど、私はほとんど食事を取れなくなった。フルーツを少し口にした程度だった。
生肉自体は、今でも好きだ。
だからこそ、この体調不良は「文化が合わなかった」という単純な話ではない。
量、環境、慣れ、それらのバランスが崩れた結果だったのだと思う。
好きだからこそ、無理がきかなかった。
それは、「文化」としてではなく、「身体」としての限界だった。
回復後に選んだ中華

2日間ほとんど何も食べられないまま過ごしたあと、ようやく体調が少し戻ってきた。
食べたいものがあるわけではなかった。ただ、ようやく何かを口にできそうな感覚があった。
GoogleMapで日本食レストランを検索しても、エチオピアでは見つからない。
そんなとき、私が選んだのは現地にある中華料理店だった。配車アプリでタクシーを呼び、すぐに中華料理店に向かった。
スパイス麺と遠くて近い味
選んだのは、スープ麺だった。
日本の中華とは違う。スパイスの効いたスープに、うどんのような太めの麺が入っている。
見た目はエスニック寄り。味も独特だった。けれど、それでも「おいしそう」と思った。
例えるなら、カレーうどんのようなスパイス感。中華でありながら、どこかアジアの記憶をまとっていた。
初めて「ほっとする」と感じる食事だった。
現地の料理を離れることに、後ろめたさがなかったわけではない。
現地のお店に比べても、少し高いと感じるような価格設定だ。
だが、それよりもまず「食べられる」ことが嬉しかった。
無理をすることをやめて、自分の感覚に正直になった食事だった。
はじめて「遠くに来た」と感じた
私はこれまで、海外で日本食が恋しくなったことがなかった。
どこに行っても現地の食に順応できたし、特別な違和感を感じることも少なかった。
それなのに、このときは「遠くまで来た」と感じた。
それは味の違いではない。たぶん、自分の中に「戻る場所」を求めていたからだ。
エチオピアの文化がどうこうではない。
ただ私にとっては、この国の食との距離が、ほかの国よりも遠く感じられたのだと思う。
その距離を埋めようとしていた数週間。
そして、それを無理に埋めなくてもいいと思えた、この一杯の中華スープ。
それは、文化との付き合い方をほんの少し変えてくれた出来事だった。
まとめ|合わせすぎなくていいと気づいた
「郷に入っては郷に従え」──それが旅の基本だと思っていた。
実際、それは正しい。文化に身を委ねたときにこそ見えてくるものがある。
しかし、合わせきれないインジェラの連続に、身体が静かにブレーキをかけていた。
「すべてに合わせなくてもいい」
その当たり前のことを、私は食を通してやっと思い出した。
これまでの私は、型にはまらない生き方をしてきた。
就職、結婚、家を買う。そういった「王道の人生」から少し距離をとって、自分なりの道を選んできた。
けれど30代になって、少しずつ考え方が変わり始めていた。
そろそろ自分も、周囲と同じような道を歩くべきなのかもしれない。そんな思いが、どこかにあった。
けれど、たかが食事、されど食事だった。
無理に慣れようとして体調を崩し、思い出したのは、自分が本当に望む「自然なリズム」だった。
周りのの生き方に合わせようとすること自体は悪くない。
けれど、それが「無理をしてまで完全に」である必要はないのだと思う。
旅の中で、それをもう一度、自分の身体が教えてくれた。