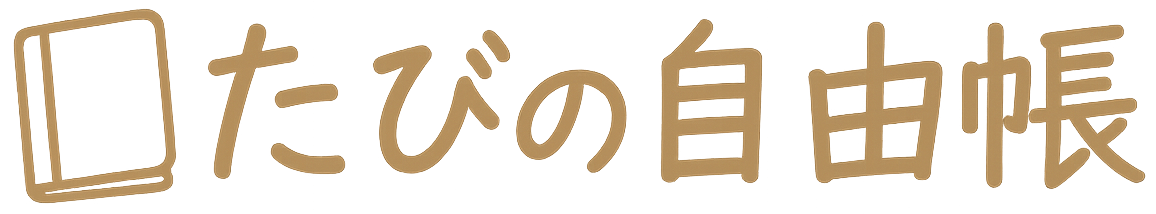「世界でもっとも到達困難な教会」と呼ばれるその場所は、観光地というよりも、何かに試されるような場だった。
エチオピア北部、ティグレ地方にある「崖の上の教会」は、私の心を強く揺さぶった。
断崖をよじ登り、素手と裸足で岩をつかみながら、谷底を背に一歩ずつ進む。
頂にたどり着いたとき、そこにあったのは、石で造られた小さな教会だった。
そのときの私は、まだ何も知らなかった。
この教会があるティグレ州が、つい最近まで激しい紛争の舞台だったことも。
人々がどれほどの痛みと沈黙の中にいたのかも。
いや、知らなかったというより「気づかなかった」と言った方が正確かもしれない。
あの絶景と祈りの空間を通り過ぎてからしばらくして、ようやく知った事実の数々。
そして、「何も知らない者が旅をすることの意味」と向き合う時間が始まった。
天へと続く道:アブナ・イェマタ・グーの断崖で
ティグレ地方を訪れた理由のひとつが、この断崖に建つ教会だった。
エチオピアの広大な大地と空を見下ろす絶壁の上。
人々が何世紀も前からそこに祈りを捧げてきたという事実に惹かれ、私はこの場所を目指した。
実際にその場に立ったとき、私の旅は静かに変わり始めた。
ただ美しい場所を訪れたつもりだった。だが、その美しさの中には、知らずに通り過ぎてはいけない何かが眠っていた。
手と足だけを頼りに登る、空とつながる教会

「教会に行く」という言葉からは、舗装された道や穏やかな礼拝堂を連想するかもしれない。しかし、ここは違った。
アブナ・イェマタ・グーへの道は、鎖も手すりもない断崖である。裸足になり、岩肌にしがみつくようにして登る。
私の背後には、谷底がはるか下に広がっていた。足を滑らせれば命を落とすかもしれないという恐怖が、ずっとつきまとっていた。
それでも、地元のガイドは笑いながら先に進んでいく。手慣れた様子の彼に引きずられるように、私は黙ってあとを追った。
それは「体験」というよりも、「通過儀礼」に近い感覚だった。教会に近づくにつれ、自分がこの世とあの世の間に立っているような気がしていた。
静寂と恐怖が混ざる、聖域での時間

崖の頂上にたどり着いたとき、視界が一気に開けた。足元の不安定さはそのままだったが、空と山々が一面に広がっていた。
教会の中は、ひんやりとした空気に包まれていた。
岩に直接描かれた聖人画、狭い空間、外から差し込む淡い光。人の営みがほとんど介入していない、純粋な祈りの場だった。
何世紀も前から、この空間は変わらぬ姿で祈りの場であり続けてきた。
それをいま、自分が「観光」として訪れていることに、言葉にできない違和感があった。
あのとき私は、ただ「美しい」と思っていた

私にとって、この教会は「絶景スポット」だった。
あの空の青さも、風の音も、すべてが心を満たしてくれた。
けれど、「知らなかった」ことに、あとになって気づく。
私はこのとき、祈っていたわけではない。
ただ、この場所を「美しい」と思った。それだけだった。
街で出会った大学生

崖の上の教会を訪れる前日、私はティグレ地方の都市・メケレに滞在していた。
観光地らしさのない、落ち着いた地方都市の空気を味わいたくて、街をぶらぶらと歩いていたときのこと。ふとした偶然から、現地の大学生と出会った。
ただの立ち話のつもりが、いつのまにか彼の案内で大学構内を歩くことになった。
学校や友達の話、未来の夢。
何気ない会話だったはずなのに、後になって思い返すと、彼の言葉や態度には深い意味が含まれていたように感じる。
あのとき私は、まだ何も知らずに、彼の言葉の行間を素通りしていた。
出会ったのは、ただの偶然だった
商店街の前を歩いていたとき、「Hello」と少しぎこちない英語が聞こえた。
話しかけてきたのは、食堂のなかにいたひとりの青年だった。
少し警戒しながらも彼の誘いに応じ、ビールを一杯注文した。
会話は弾んだものの、せっかくメケレに来たので日が暮れる前に街を少し散歩したいと席を立とうとすると私に、「一緒に行ってもいい?」と控えめに聞く彼。
もちろんと二つ返事で了承して少し散歩した。
散歩をしながら彼がそばの大学に通っている大学生だとわかり、ぜひ案内してほしいとお願いした。
キャンパスを歩きながら交わした、まっすぐな言葉

大学の中は広く、緑が多く、歩いているととても穏やかな気持ちになった。
途中で出会った彼の友人も一緒になり、みんなで校舎や食堂の前を通りながら、笑い合った。
「もうすぐ暗くなるけど、この辺りは安全なの?」と私が聞くと、彼は一瞬だけ言葉に詰まり、それから「大丈夫だよ」と答えた。
その笑顔が少しだけ不自然に見えたのは、気のせいだったのかもしれない。
彼はそう言わなければならない立場だったのかもしれない。
私の問いかけに対し、彼の返答は慎重で、それでいて誠実だった。
彼の沈黙とやさしさが、後になって問いに変わった
あのとき私は、ただ「親切な学生と過ごした穏やかな夕暮れ」として、すべてを記憶にしまい込んでいた。
だが後になって、彼のいくつかの沈黙や目線の動きが、妙に引っかかっていたことに気づいた。
何も語らなかったこと。それが、語れなかったのか、それとも語らなかったのか。
私にはわからなかったが、あの静けさは何かを守るためのものだったのではないか、と今は思う。
彼の未来を応援したいと思ったし、彼のいる世界に何が起きていたのかを、もっと知りたくなった。
それは、教会での静寂とはまた違う種類の「問い」を、私の中に残していた。
ティグレ州で起きていたこと

私が旅をしていたその頃、この土地では何も起きていないように見えた。
だがあとになって、私はその「静けさ」が、単に私の無知の上に成り立っていたことに気づいた。
ティグレ紛争。
2020年に始まったその内戦では、数万人が犠牲になったとされる。
国際報道は長く制限され、何が起きていたのかを正確に知ることすら難しい。
けれど、断片的に伝わってくる数字や証言、そして破壊された教会の映像が、この場所のもう一つの顔を静かに浮かび上がらせていた。
私は、何も知らずにその土地を歩いていた。
まるで、何もなかったかのように。
旅のあとに知った、もう一つのティグレ
私はティグレを旅したあと、たまたまインターネットで「ティグレ紛争再燃の懸念」という見出しを目にした。
最初は、その言葉の意味さえよく分からなかった。
スマートフォンで検索を始め、英語の記事を読み、ようやく全体像の一端が見えてきた。
ティグレ州は、かつてエチオピア政権を実質的に率いたTPLF(ティグレ人民解放戦線)の拠点だった。
しかし政権交代とともに周縁化され、やがて連邦政府との間で衝突が始まった。
その過程で、通信は遮断され、支援は届かず、村ごと消えたとも言われている。
私はそんな場所にいた。
そして何も知らずに、普通に旅をしていた。
だがそれは、私だけの錯覚だったのだろうか。
それでも誰も語らなかったのはなぜか
私は思い返す。
メケレの街を歩いたときも、教会を案内してくれたときも、ガイドや大学生たちが「紛争」という言葉を一度でも口にしたことはなかった。
それが彼らの優しさだったのかもしれない。
あるいは、話してはいけない空気があったのかもしれない。
あるいは、日常を守るために、あえて話さなかったのかもしれない。
どの可能性も否定できない。
けれど少なくとも、私は「観光客」として扱われていた。
そして、「観光地」として振る舞っていた。
その距離感が、今になって苦い後味を残している。
なぜエチオピアでは民族が政治になるのか
※このセクションでは、少しだけ歴史と政治の背景に踏み込みます。旅の体験だけを読みたい方は、読み飛ばしても問題ありません。
エチオピアを旅していると、何度も耳にする言葉があった。それは、民族という単語。街の会話やガイドの説明の中に、ごく自然に民族という言葉が入り込んでいる。それは、日本で暮らしていた私にとっては、少し異質な光景だった。なぜなら日本では、政治を語るときに「自分は〇〇民族だから」という言い方をすることはまずないからだ。
だが、エチオピアでは違った。
国の政治が、はじめから民族という単位を前提として組み立てられている。それは、ただ文化や言語が違うというだけの話ではない。エチオピアという国そのものが、民族ごとに割り振られた州の集合体であり、政党もまた民族単位で構成されてきた。
この仕組みは「民族連邦制」と呼ばれる。
一見すると、各民族の自立性を尊重する民主的な仕組みにも思える。だが現実はもっと複雑で、民族間の力関係や歴史的経緯が複雑に絡み合い、やがて国家そのものを引き裂く要因にもなっていった。
ティグレ紛争もまた、その延長線上にあった。
私が見ていたのは、ただの民族の多様性ではなかった。
そこには、国家の枠組みそのものが揺らいでいるという、もう一つの現実があった。
なぜ政党が民族ごとに分かれているのか
エチオピアでは長らく、政党と民族は一体のものとして存在してきた。
その象徴が、1991年から続いたEPRDF(エチオピア人民革命民主戦線)という与党連合だ。これは複数の民族政党からなる連合体であり、中心にいたのがTPLF(ティグレ人民解放戦線)だった。他にも、アムハラ人を基盤とするANDM(アムハラ国家民主運動)や、オロモ人のOPDO(オロモ人民民主機構)などが名を連ねていた。つまり、与党そのものが民族ごとの代表によって構成されていた。
だがその構造は、あくまで建前上の平等だった。
実際には、少数民族であるティグレ人のTPLFが軍事力と政治の両面で影響力を持ち、国全体をリードしてきた。これは、TPLFが内戦を制して政権を獲得したという歴史に基づくもので、1990年代以降、軍・治安・経済の中枢は彼らが握っていたと言われている。
この構造に対して、不満を募らせていったのが他の民族政党だった。特にオロモ人は、人口比で最も多いにもかかわらず、政治的には過小評価されていたと感じていた。
そして2018年、この不満が大きな転機を迎える。
EPRDF内部から選ばれたのは、オロモ系政党出身のアビー・アハメド氏だった。
彼の登場は「変革」の象徴として歓迎されたが、それは同時に、長らく権力を握ってきたTPLFにとっては「敗北」を意味していた。
エチオピアの政党が民族ごとに分かれているのは、制度としてそう決められていたからではない。
それは、国家という単位よりも先に、「自分たちの民族」という単位が政治の根っこにあったからだ。
そしてその構造は、今も完全には変わっていない。
繁栄党とTPLF:割れた国家像
アビー・アハメド政権が誕生してまもなく、彼はEPRDFの解体と、各民族政党の統合を進めた。
こうして誕生したのが「繁栄党(Prosperity Party)」だ。
表向きは民族間の分断を乗り越え、「一つのエチオピア」を目指す政党。過去の民族連合型政権からの脱却という点で、近代国家への一歩とも評価された。
だが、それはすべての民族に歓迎されたわけではなかった。
TPLFはこの統合に最後まで反対し、唯一参加を拒否した。彼らは「繁栄党」が掲げる統合の理念を、中央集権的でティグレ州の自治を損なうものだと受け止めていた。
首都アディスアベバから見れば、繁栄党は「国家の一体性を目指す改革政党」かもしれない。
だがティグレ州から見れば、それは「中央政府による支配の強化」だった。
こうして、かつては同じ与党連合に属していたTPLFと他の政党は、急速に距離を広げていった。
その溝は、2020年にティグレ州が独自に地方選挙を強行したことで決定的となる。
連邦政府はこれを違憲とし、TPLFも反発。やがて、軍の衝突に発展した。
今も続く火種たち
2022年にいったん停戦が成立し、ティグレ紛争は終結したかのように見えた。
だが、火種は消えていない。
エチオピア各地では、今も武力衝突が断続的に起きている。ティグレ州だけでなく、オロミア州やアムハラ州でも不安定な情勢が続く。
繁栄党は民族政党の枠組みを越えた統合国家を掲げているが、その下でも多くの民族が自分たちは周縁化されていると感じている。
とりわけ、オロモ人の中にはアディスアベバは自分たちの土地だと主張する者も多い。だが都市の実権は長くアムハラ人や連邦政府が握ってきたという認識が根強く、奪われた首都として都市を見る感覚は、容易には消えない。
こうした認識のずれが、政治的な緊張となって現れる。つまり、ティグレ紛争の背後にあったのは単なる政党間の対立ではない。
国土の広さ、多様な民族、複雑な歴史。エチオピアという国の地図には、目に見えない境界線がいくつも存在している。
あの旅を、もう一度読み直す
ティグレの岩山を登り、教会を訪れ、静寂のなかで祈るような時間を過ごしたあの日。
私はその旅を通して、ただ「美しい場所に来た」とだけ思っていた。
けれど旅が終わったあと、私は少しずつ現実を知っていくことになる。
かつてこの地が、政権の中枢を担っていたこと。
やがて周縁化され、内戦の舞台となったこと。
そして、私が歩いていたその場所が、誰かにとっては「傷」の記憶と重なる場所でもあったということ。
観光地として紹介される風景の裏側に、語られなかった歴史がある。
誰もそれを教えてくれなかったのではなく、私が知らなかっただけなのだ。
私は今も答えを持っていない。
旅人が、どこまで社会問題に目を向けるべきなのか。
無知なまま訪れたことに、どれだけの意味があるのか。
けれど少なくとも、あの旅を「ただの思い出」にしないために、私はこうして書いている。
あの断崖の上の教会が、私に問いかけてきた静けさの意味を、ようやく少しだけ受け止められた気がするから。