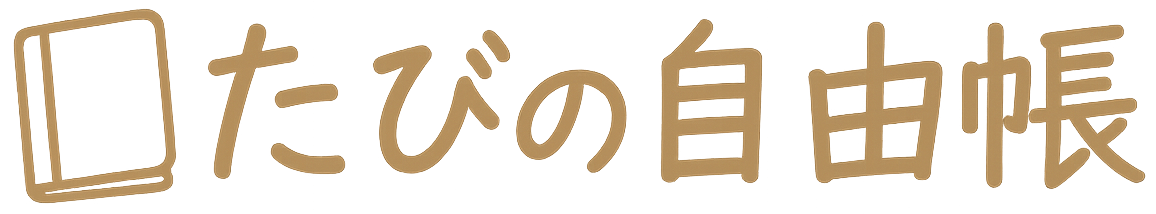エチオピアで腹を壊した。
生肉を食べたあとだった。腹痛だけでなく、熱もめまいもあった。持ってきた市販薬はまるで効かず、横になっていても苦しかった。
タクシーを呼び、近くの薬屋へ向かった。
いくつか症状を聞かれたあと、処方箋なしで抗生物質が出てきた。薬剤師なのかどうかもわからない。でも、言われるがままに買って飲むと、数日後には体調が戻った。
ただ、それで終わりではなかった。
助かったのに、どこか引っかかった。
街の薬局で薬を買った経験

薬屋は小さな店だった。看板には薬の名前が並んでいたが、外から見ただけでは営業しているのかどうかもわかりにくい。中に入ると、カウンターの奥に棚があり、箱に入った薬が積まれていた。
カウンター越しに体調を伝えると、店員はこちらの様子を見ながらいくつか質問をしてきた。どこが痛むのか、熱はあるのか、下痢は続いているのか。英語は通じ、質問も丁寧だった。説明も分かりやすく、薬の使い方や服用回数についてもしっかり伝えてくれた。
渡されたのは抗生物質だった。処方箋は求められなかったが、やり取りに違和感はなかった。価格も安く、数百円程度だったと記憶している。
私はたぶん、良い薬屋にあたったのだと思う。医者に診てもらったわけではないし、検査をしたわけでもない。けれど、少なくともその場では安心感があった。そして実際に、薬は効いた。
薬の入手と意外な手軽さ
日本なら、抗生物質をもらうには病院に行き、医師の診察を受け、処方箋を書いてもらわなければならない。薬局はそのあとだ。そこには時間も手間も費用もかかる。
でも、あのときの私は、体調を伝え、数分会話を交わしただけで薬を手に入れた。しかも抗生物質だった。
薬屋の対応は丁寧だったし、不信感を覚えたわけではない。それでも、日本で育った自分にとっては、その「簡単さ」そのものが驚きだった。良い薬屋に当たったという運の良さを感じつつも、どこか現実感のないまま、薬の箱を手にしていた。
正しさとのずれと実感
そのときは、薬が効くかどうかしか考えていなかった。
とにかくつらくて、早く治りたかった。それがすべてだった。
店員が薬剤師かどうかも、処方箋が必要かどうかも、頭をよぎったかどうかすらあやしい。あの場で私が求めていたのは、正しさではなく、薬だった。
薬を飲んで、数日後に体調が戻った。
それで十分だったはずなのに、なぜかその出来事があとになって残った。
「これは普通じゃなかったんじゃないか?」という違和感が、少し遅れてやってきた。
それは不満ではなかった。ただ、自分が当然だと思っていた仕組みが、この場所では違ったという事実が、静かに心に引っかかった。
医療制度とその現実

日本であれば、今回のような症状なら病院に行って、医師の診察を受けて、薬を処方してもらうというのが自然な流れだったと思う。私自身、ずっとそうしてきた。
エチオピアにも、そうした医療制度がまったく存在しないわけではない。病院もあるし、薬局の制度や資格の枠組みも整備されていると聞く。
でも、今回の経験を通じて感じたのは、その制度が「現実として使える形で存在しているか」といえば、必ずしもそうではないということだった。
都市部にいて、英語が通じ、アクセスに恵まれていた私ですら、迷わず薬屋に向かった。そうするのが一番早くて、確実で、現実的だった。
制度はある。けれど、誰もがその制度の中で生きているわけではない。そんな感覚が、あとからじわじわと残った。
制度としての医療の仕組み
エチオピアの医療制度は、決して無秩序というわけではない。
都市部には総合病院もあり、薬局には資格制度が存在する。抗生物質などの医療用医薬品も、原則としては薬剤師の管理下で扱うことになっている。感染症やワクチン接種などについては、国際機関の支援も受けながら体制が整えられてきたという。
仕組みとしては、あくまで存在している。
ただ、その制度がどれほどの人にとって「使えるもの」として機能しているかは、また別の話だと思う。
病院までの距離、待ち時間、費用、言葉、専門家の不足。それらの障壁を前に、制度の存在そのものが現実から遠ざかっていく。
私が訪れた薬屋も、その制度の枠の外にあったのかもしれない。
そして、利用していた私は、その制度の存在を意識することはなかった。
届かない制度の限界
制度があっても、それが人々にとって実際に届くかどうかは別の問題だ。
医師や薬剤師の絶対数が足りていない。特に地方では、病院どころか診療所すらない地域も珍しくない。医療従事者が都市部に集中しているため、制度の網の目は広がっていても、その隙間にこぼれ落ちる人が多い。
都市部にいても、病院に行くにはお金と時間がかかる。外国人である私ですら、手間や言語の壁を考えて病院を選ばなかった。では、地元の人はどうか。毎日の暮らしで精一杯の中、少しの体調不良に何時間もかけて通院することは現実的ではないのかもしれない。
その結果、制度があっても、多くの人はそれを通らずに薬屋に向かう。資格の有無は曖昧で、診察もない。それでも、そこで薬を手に入れられれば、その日を乗り切ることができる。
正論が人を救えないとき
処方箋もなく、検査も受けず、抗生物質を飲んで回復した。
あれは明らかに、日本の医療制度では認められないやり方だった。
それでも私は助かった。
その事実の前では、「正しかったかどうか」という問いは、どこかかすれてしまう。
あとになって考えるようになった。
あの場で「処方箋が必要です」と言われていたら、私はどうしていただろうか。
高熱と腹痛を抱えたまま、慣れない土地で病院を探して移動し、順番を待ち、英語で説明し、ようやく薬にたどりついていたのだろうか。それが現実的だったのかどうか、今でもわからない。
制度には意味がある。ルールにも理由がある。
でも、もしそれが命に届かないなら、正しさとはいったい何を守っているのか。
薬を乱用して体を壊す人もいるだろう。偽薬で命を落とす人もいるかもしれない。
けれど、制度の外側にしか救いがない人がいるのも確かだ。
違法な薬で助かる人と、制度にたどり着けずに亡くなる人――どちらの方が多いのかは、私にはわからない。
ただ、あのとき私は「制度を守る」側ではなく、「制度の外で救われた」側にいた。
だからこそ、今の私はもう、あれを「正しくない」とは言えない。
そして、それを「正しい」とも言い切れないまま、ずっと答えの出ない場所に立ち続けている。