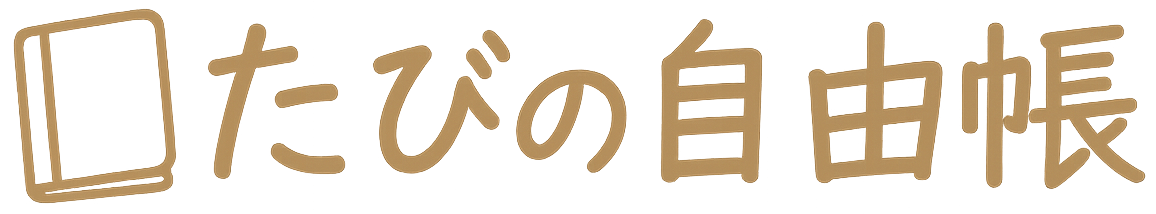アディスアベバの街角で、少年たちが近寄ってきた。
手には使い込まれたブラシと布。私の靴をじっと見つめ、靴を磨くジェスチャーをする。
私は首を横に振り、その場を離れた。
関わると面倒だから。旅先ではよくあることだから。
そう言い聞かせながら、心のどこかで「貧しい子どもたちが気の毒だ」と思っていた。
それが間違いだったとは思わない。
でも、あの瞬間、彼らを「貧困」とラベリングして距離を置いた自分がいた。
あのときの選択の裏に、自分の限界があったことは否定できない。
都市開発の裏にある見えない記憶

アディスアベバの第一印象は、意外なほど整った道路だった。 私が最初にそれを口にしたのは、現地ドライバーとの車中だった。「道路がきれいで驚きました。車道も歩道も、自転車道まである」。そう話すと、ドライバーは驚いた様子もなく頷いた。 「今年に入ってから、一気に整備されたんだ」。
そのとき車を運転していたドライバーが教えてくれた。この道路が整備されたのは今年に入ってからで、ほんの数ヶ月で一気に仕上がったという。たしかに、どこか出来たてのような匂いが残っている気がした。
整備された都市。私はその言葉に何の疑問も持っていなかった。けれど、彼との会話を続けるうちに、その裏に別の風景が見え隠れするようになった。
立ち退きをめぐる声と整備のスピード
ドライバーは、整備が急だったことを繰り返し話していた。そしてその過程で、もともとこの道路沿いに住んでいた人々が立ち退きを余儀なくされたとも教えてくれた。屋台で生計を立てていた人、路上で暮らしていた人、建物の隙間に住んでいた家族。彼らはどこかへ移され、今はその痕跡すら残っていない。
アディスアベバの住民の多くはこうした政府の行政に対して、不信感を募らせているそうだ。
私が「整っていてすごい」と言った場所には、つい最近まで、誰かの日常があった。そう聞かされたとき、自分の足元の印象が少しだけ変わった気がした。
正しさとして語られる再開発
別の日、都市ツアーを担当してくれたガイドにも、道路整備について尋ねてみた。すると彼は、「政府はちゃんと代わりの住居を提供しているよ。だから問題にはなっていないはずだ」とはっきり答えた。整備は制度に基づいて正しく進められており、住民も納得しているという前提があった。
彼の語りには、混乱や抵抗といった言葉は一切なかった。むしろ、この再開発がこの街をより良くしているという確信があったように感じられた。
二人の話は矛盾しているわけではない。けれど、そのあいだにある温度差が、妙に気になった。整備という言葉が持つ明るい響きと、その過程で語られないもの。その落差が、頭から離れなかった。
都市の風景が語らなくなるとき
それ以来、私は歩道を歩くときに、ほんの少し足元を気にするようになった。
整備された道は、歩きやすくて美しい。けれど、その下に何があったのか、誰がそこにいたのかを知ることはできない。人の暮らしは、必ずしも記録に残るわけではない。整備とは、そうした説明されないものを覆ってしまうことなのかもしれない。
私はそのことを批判したいわけではない。ただ、自分が感動していた風景の裏側に、消えてしまった風景があるということを、知ってしまった。
メルカト市場に見るもう一つの都市

整った都市には整った生活がある。そう思っていた私の足元には、買いたい物すら手に入らない現実があった。
アディスアベバに2週間ほど滞在してみて、まず感じたのは「買い物の難しさ」だった。近代的なショッピングモールは見当たらず、スーパーマーケットと呼べるような店もごくわずか。ビルはあるが、必要なものが買えるわけではない。アパレル中心の小さな商店は多いが、品揃えは限られていた。
そんななかで、現地の人たちが日用品や食料、家電、寝具まで手に入れている場所がメルカト市場だ。雑多で迷路のようなエリアだが、仕入れルートさえわかっていれば、ほとんどの物が手に入る。現地の人にとっては、ここが実質的な「モール」なのだ。
観光客の私にとっては少しハードルが高かった。必要最低限のものは、近所の一畳ほどの小さな雑貨屋で買っていた。それでも、市場の内部を見て回ると、都市の物流や生活の実態が、この場所に凝縮されていることが分かってくる。
帳簿に残らない都市の経済活動
メルカト市場では、商品が整然と陳列されているわけではない。仕入れのルートもすべてが正規とは限らない。だが、人と人の関係のなかで価格が決まり、取引が成立し、暮らしが成り立っていた。
都市の商店もまた、多くはこの市場を通じて商品を仕入れている。ここはただの混沌ではなく、都市の経済を実際に支える巨大な流通拠点だった。
たとえば、郊外の小売店や路上の露店に並ぶ商品も、その多くがこの市場を起点に動いているという。表通りの美しいショーウィンドウの裏側にある、見えない物流の源、それがメルカトだった。
この街には、語られない風景がある。帳簿に載らない取引があり、制度には現れない選択がある。
発展の途中にある都市だからこそ、整った言葉では捉えきれない何かが、足元から立ち上がってくる。
都市の中心を、別の角度から見直す
アディスアベバの表通りに立つと、再開発によって整備された風景が目に入る。だが、そこで何が手に入るかと問えば、実際の生活とはかけ離れていることも多い。ビルはあっても、暮らしは満たされていない。
一方でメルカト市場には、生活のすべてが揃っていた。見た目の整備はなくても、声を張り上げる商人、身振りで交渉をする買い手、荷を運ぶ若者たち――そのすべてが都市を支えている。
都市の発展を、私はどこで感じればいいのだろうか。建物の高さや道路の広さでは測れない、もう一つの「中心」が、この市場には確かに存在していた。それは、都市の整備ではなく、都市の営みそのものだった。
足元にあった、もう一つの都市

都市を歩きはじめたとき、まず目に入ったのは道路の整備状況だった。中心部の一部には、舗装された道や新しい建物が立ち並び、発展を象徴する風景もある。だが、ほんの少し脇道に入れば、道はでこぼこになり、土埃が舞うエリアが広がっていた。アディスアベバは今まさに再開発の最中にある。完成された都市というよりは、発展の途中段階でさまざまな表情を見せる場所だ。
そんな街を歩いていると、物乞いをしている大人たちの姿が目に入る。そのすぐ隣では、少年たちが黙って私の足元を指さし、靴を磨かせてほしいとジェスチャーをしてきた。都市の整備ばかりに気を取られていた私は、この街の足元で、まったく別の営みが息づいていることに気づかされた。
物乞いではなく、仕事を求めて
アディスアベバの街角には、道ゆく人に手を差し出す大人たちがいる。一方で、私が強く印象を受けたのは少年たちだった。彼らは物乞いをするのではなく、自分の手で稼ごうとしていた。彼らは英語を話さない。けれど、視線と身振りだけで、自分が何を望んでいるかを的確に伝えてくる。
はじめてその光景を見たとき、私は「児童労働」という言葉を思い浮かべた。貧しさが子どもたちを働かせている。そう感じたのは、きっと私だけではないと思う。だが、彼らは物乞いとは違う「何か」を選んでいた。
線を引いたのは、私のほうだった
私は、靴磨きの申し出に応じなかった。彼らの生き方を否定するつもりはなかったが、どこかで自分の中に葛藤があった。「関わってはいけないもの」「倫理的に線引きすべきもの」。そんな曖昧な感覚のまま、私は歩き続けた。
彼らのまなざしがしばらく背中に残っていた。私が何に対してためらっていたのか、当時はうまく言語化できなかった。ただ、その一瞬の交差が、この旅の視点を変えていく最初のきっかけになったのは間違いない。
磨かれた靴と、曇った私の視点
少年たちの姿が頭から離れないまま、私はある日、大人の靴磨き職人に出会った。観光地近くで立ち止まっていたとき、彼は無言で磨くジェスチャーを見せ、私は靴を差し出した。理由ははっきりしなかったが、その所作に静かな誇りを感じたのかもしれない。
彼はほとんど英語を話さなかったが、動きには迷いがなく、何度も布を当て直す手つきには、長年の経験がにじんでいた。靴は見違えるほどに輝き、私は素直に感心した。
そのとき、私は通りで出会った少年たちの姿を思い出していた。言葉がなくても、彼らは何かを伝えようとしていた。あの職人のような未来を歩む姿を想像したわけではない。だが、自分の手で稼ぐという行為の中に、共通する力強さを感じたのだ。
磨かれた靴は光を取り戻したが、私の視点はまだ曇ったままだった。
少年たちの姿が、ただの「貧困」でも「労働」でも語りきれないことだけは分かっていた。
その問いに、一つの答えをくれたのは、後日出会ったガイドの青年だった。
彼らは、可哀そうではなく、賢い

靴磨きをしていた少年たちを思い出していたとき、私はあるガイドと出会った。彼は私の旅を案内してくれる立場にいたが、その生い立ちや考え方は、都市の表と裏を知る“語り部”のようでもあった。
彼の話を聞くうちに、私はそれまで「貧しさ」としてしか見えていなかったものが、まったく違ったものに感じられてきた。彼が語ったのは、同情ではなく、そこに生きる人たちのしたたかさ、そして前向きさだった。
選び直された人生
彼は、貧しい家庭に生まれたという。若い頃はナイトクラブで働き、薬にも手を出したことがあると、淡々と語ってくれた。それでも今は、ツアーガイドとして働きながら、自力で大学にも通っているという。
その語り口に、自分の過去を恥じるような様子はなかった。むしろ、その経験を通じて「どう生きるか」を選び直してきたようだった。観光案内という表の顔の裏に、彼自身の複雑な人生が重なって見えた。
「可哀そう」という視点を超えて
私が靴磨きの少年たちの話をしたとき、彼は即座に「彼らは賢い」と言った。
その言葉に私は少し驚いた。「貧しい子どもたち」という見方を、彼は明確に拒んでいた。
彼によれば、彼らは自分の道具を持たずに、仲間とシェアしながら暮らしているという。住む場所も一緒で、情報も共有し、支出を抑え、稼いだ金を貯金している。何よりも、彼らは自分たちの未来に対して、すでに“戦略”を持っているのだと語った。
その話を聞いたとき、私はまた、彼らの姿が頭に浮かんだ。彼らはただそこに「居た」のではなかった。自分の足で立ち、自分のやり方で生きていたのだ。あの無言のジェスチャーは、単なる必死さではなく、意志そのものだったのかもしれない。
彼らは可哀そうじゃない、賢いんだと言うガイドの言葉。たしかにそう思える一面もあった。
でも、あの少年はやっぱり貧しかった。日本の感覚で言えば、そうなる。
そして私は、その「貧しさ」に対して線を引いた。
関わらないことで距離を保ち、見ないことで自分を守ったのだと思う。今なら、そう言える。
あのとき、私が靴を磨いてもらったのは少年ではなく、大人の職人だった。
それが間違いだったとは思わない。でも、あの選択の裏に、自分の限界があったことも否定できない。
この都市で、私は「見る」ことを学び直した
私はたぶん、見ようとしていなかったのだと思う。
「関わると面倒だ」とか、「どこかで線を引かなくちゃ」とか。
自分を守るように、見なかったことにしていた場面が、いくつもあった。
ガイドの言葉がすべて正しいとは思わない。
でも、彼のような視点を持っていれば、私はもっと近づけたのかもしれない。
「正しさ」や「常識」じゃなくて、自分の目で見るということ。
関わることを恐れず、説明できないことからも目をそらさずに、これからの旅を続けていきたい。
言葉にできない感情も、うまく整えられない経験も、それごと受け止めながら、私は自分の足で歩いていく。