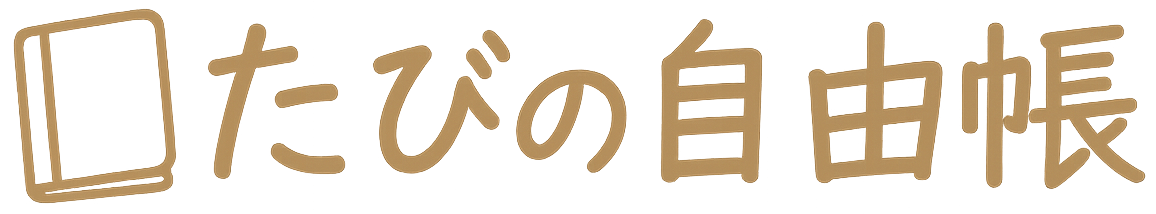海外を旅しながら働くノマドワーカーにとって、「税金」の問題は避けて通れません。どこに居住しているのか、どの国で収入を得ているのかといった条件によって、税務上の扱いは大きく変わります。
私自身も、会社員からフリーランスを経て法人化し、現在は日本に住民票を置いた「居住者」として登録されています。非居住者という選択肢も検討しましたが、節税よりも生活や事業の快適さを重視して、あえて日本に居住地を残す形を選びました。
この記事では、「居住者/非居住者」の違いやその影響、手続き上のポイント、そして制度と現実を照らし合わせた上での私自身の判断軸をお伝えします。自由な働き方を続けながらも、納得のいく形で制度と向き合いたい方にとって、現実的な指針になれば幸いです。
海外ノマド・フリーランスが向き合う税金とは?
海外を拠点に働くノマドワーカーやフリーランスにとって、税金の問題は単なる手続きの話ではなく、生活や働き方の根幹に関わるテーマです。どの国にどれだけ滞在し、どの国から収入を得ているか。日本にどの程度の「つながり」が残っているか。こうした条件によって、税の扱いは大きく変わってきます。
特に重要なのが、「どこに住んでいるとみなされるか(=居住地)」という考え方です。これは、所得税や住民税、社会保険の加入義務、確定申告の方法などに直結するため、最初に明確に理解しておくべきポイントになります。
この章では、まず海外ノマドが関わる主な税金と社会保険制度を整理し、そのうえで「居住地」ついて解説していきます。
主な税金と社会保険
海外ノマドやフリーランスとして活動する場合でも、日本の「居住者」として扱われる限り、国内と同様の税金や社会保険制度に関わる必要があります。具体的には、以下のような制度が該当します。
- 所得税:日本の居住者であれば、全世界で得た所得に対して課税される「全世界所得課税」の対象になります。
- 住民税:1月1日時点で日本に住民票がある場合、前年の所得に基づいて課税されます。
- 個人事業税:事業所得が年間290万円を超える場合、都道府県から課税される税金です。ただし、住民票を抜いた非居住者には原則として課税されません。
- 消費税:前々年の課税売上が1,000万円を超える場合に納税義務が発生します。さらに、2023年10月から導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、免税事業者であっても課税事業者としての登録を選択するケースが増えています。制度上の立場と取引実務とのズレに注意が必要です。
- 国民健康保険(国保)/社会保険:個人事業主であれば国保と国民年金、会社員や法人代表であれば社会保険の加入対象になります。
- 年金:海外に長期滞在しても日本国内に住所があれば、原則として加入義務が継続します。
これらの制度は、「どこで働くか」よりも「どこに住んでいるか」によって判断されることが大半です。
こうした背景から、「日本に居住しているかどうか」は、税務上も社会保険上も非常に重要な判断基準となるのです。
「居住地」が重要になる理由
課税の基準は「居住者」か「非居住者」かという区分によって大きく異なります。
たとえば、居住者であれば全世界で得た所得すべてが日本での課税対象となります。一方、非居住者になると、日本国内で得た所得(国内源泉所得)のみに課税され、それ以外の所得は原則として日本では課税されません。
また、住民税や国民健康保険、年金といった制度も、「日本に住所があるかどうか」を基準に加入義務や課税の有無が決まります。住民票を抜いた場合はこれらの義務から外れることもありますが、それによって発生するデメリット(年金の未加入期間や医療費全額自己負担など)も考慮する必要があります。
つまり、「居住地」の選択は、節税だけでなく、社会保障や生活の安心に関わる要素まで含んだ重要な判断になります。この後の章では、税務上の「居住者」「非居住者」の定義と違いについて、さらに詳しく見ていきます。
税務上の「居住者」と「非居住者」とは?
海外ノマドやフリーランスが税金と向き合ううえで、まず押さえておきたいのが「居住者」と「非居住者」の違いです。これは単なる住所の有無ではなく、税務上の取り扱い全体に関わる重要な区分です。
どちらに該当するかによって、所得税の課税範囲、住民税の有無、社会保険や年金の加入義務、さらには確定申告の必要性まで変わってきます。
この章では、まず税法上における「居住者」「非居住者」の定義を確認したうえで、それぞれがどのような制度や負担に影響するのかを整理していきます。
「居住者」と「非居住者」の基本定義
税法上、日本における「居住者」と「非居住者」の定義は、所得税法第2条に基づいて明確に区分されています。
- 居住者:日本に「住所」がある人、または過去1年以内に引き続き日本に「居所」がある人
- 非居住者:上記のいずれにも該当しない人(=住所も居所もない人)
ここで言う「住所」は、生活の本拠(=生活の拠点)が日本にあるかどうかが基準です。単に住民票があるかどうかではなく、実際にどこで生活しているか、滞在の実態がどうかが問われます。
一方の「居所」とは、住所ほど明確な拠点でなくても、比較的長期間(概ね1年程度以上)日本に滞在している状態を指します。つまり、住所がなくても長く日本に滞在していれば、居住者とみなされることもあります。
そのため、たとえ住民票を抜いて海外にいても、日本に生活実態が残っていれば「非居住者」とは認められない可能性がある点に注意が必要です。税務上の判断は形式よりも実態が重視されます。
非居住者の所得税・住民税・国保などの取り扱い
税務上の「非居住者」になることで、あなたの税負担や社会保険制度への関わり方は大きく変わります。以下は主な違いです。
- 所得税:海外で得た収入は日本で課税されなくなります(国内源泉所得のみ対象)。
- 住民税:住民票を抜いて非居住者になれば、翌年以降は課税されません。
- 個人事業税:都道府県税のため、住民票を抜くと課税対象外となります。
- 消費税:原則として納税義務は継続しますが、取引の所在地や内容によっては免税扱いになる場合があります。インボイス制度の登録状況にも注意が必要です。
- 国民健康保険:加入義務がなくなり、保険料も不要になります。代わりに海外保険が必要です。
- 年金:任意加入に切り替え可能。支払わなければ未納扱いになりますが、将来の受給資格に影響します。
非居住者になると、原則として日本国内に源泉がある所得のみが課税対象になります(詳細は後述)。
こうした変化は金銭的な負担を軽くする一方で、社会保障のカバーが減るという側面もあります。非居住者になる前に、どこまでリスクを取れるか、自分の生活と照らして判断することが大切です。
非居住者になるには?|手続きと制度の全体像
非居住者として扱われるには、海外転出届を出すだけでは不十分です。住民票の有無だけでなく、実際の生活拠点が日本にないことが前提とされます。
あわせて、年金や健康保険、金融機関の手続きにも注意が必要です。
この章では、非居住者となるための基本的な流れと、関係する制度の扱いを整理します。
海外転出届は必要条件にすぎない
非居住者になるための最初の手続きが「海外転出届」です。
ただし、転出届を出しただけでは、税務上の非居住者と認められるとは限りません。重要なのは、実際の生活の拠点が日本にないという「実態」です。
たとえば、頻繁に日本に戻って長期滞在している、仕事の中心が日本にあるといった場合、税務署から居住者と判断される可能性もあります。
形式とあわせて、生活の実態を移すことが非居住者として認められる鍵になります。
非居住者の社会保険・年金・マイナンバー
非居住者になると、社会保険や年金制度の取り扱いも変わります。以下の3点は特に注意が必要です。
- 国民健康保険(国保):住民票を抜いた時点で資格喪失となり、保険証は返却します。以後は医療費が全額自己負担になるため、海外旅行保険などでの備えが必要です。
- 年金(国民年金・厚生年金):強制加入ではなくなり、「任意加入」に切り替わります。未納のままでも差し支えはありませんが、将来の受給資格や金額に影響するため、希望する場合は継続手続きを取ります。
- マイナンバー:住民票を削除しても番号は残り続け、帰国後も同じ番号が再利用されます。番号自体は失効しませんが、金融機関との取引や証券口座で使う場合は現住所との整合性に注意が必要です。
非居住者になる際は、これらの制度の変化を見越して、必要な届出や代替手段の検討をしておくことが大切です。
金融機関の注意点
非居住者になると、銀行や証券口座、クレジットカードの利用に制限がかかることがあります。特に以下の点に注意が必要です。
- 銀行口座の維持:多くの日本の銀行は、規約上「国内在住者」に限定して口座を提供しています。非居住者になった場合、住所変更を受け付けない・口座を解約される可能性もあります。
- 証券口座・NISA:非居住者になると、基本的に国内証券口座の運用ができなくなります。NISAも制度対象外となり、継続はできません。
- クレジットカード:利用自体は可能でも、更新・再発行時に日本国内の住所確認が求められ、手続きが困難になることがあります。長期渡航前に必要なカードは作成・更新しておくのが安心です。
- 海外送金・本人確認:非居住者はマネーロンダリング対策の観点から、送金や大口取引で追加書類を求められるケースがあります。
長期的に日本を離れる場合は、事前に各金融機関のルールを確認し、住所や口座管理の計画を立てておくことが重要です。
海外収入と確定申告の実務
海外を拠点に働くノマドやフリーランスにとって、収入の発生場所や通貨、支払い方法が多様になるほど、確定申告の実務も複雑になっていきます。
居住者であれば、たとえ報酬が海外から振り込まれても、日本の所得税の対象となり、基本的にはすべて申告が必要です。非居住者になった場合でも、日本国内に源泉のある所得があれば、課税対象になります。
このセクションでは、「居住者」と「非居住者」で確定申告がどう変わるのか、そして個人と法人でどのように実務が異なるのかを整理します。
居住者の場合の基本ルール
税務上の「居住者」として扱われる場合、全世界で得た所得が日本の課税対象になります。つまり、たとえ海外のクライアントから報酬を受け取っていても、日本で申告・納税しなければなりません。
たとえば、現地通貨で受け取った報酬や、PayPal・Wiseなどを経由した入金も対象です。受け取った金額を日本円に換算し、その年の確定申告で申告する必要があります。
なお、海外との二重課税を防ぐために、外国税額控除を活用できる場合もあります。現地で源泉徴収された場合などは、確定申告時に忘れず確認しておくとよいでしょう。
基本的に、日本で居住者として活動する限り、収入の発生場所や通貨にかかわらず申告義務があるという前提を持っておくことが重要です。
非居住者になった場合の実務
非居住者になると、日本で課税されるのは「国内源泉所得」に限られます。つまり、海外クライアントからの報酬や、現地で発生したビジネス収入については、日本での確定申告は原則不要です。
ただし「国内源泉」の範囲は一律ではなく、たとえば日本企業からの原稿料や広告収入などは、たとえ海外で作業していても国内源泉と見なされることがあります。そのため、企業側が20.42%の源泉徴収を行うケースが一般的です。
また、日本に法人を持っていたり、実質的に拠点が日本にあると見なされる場合は、非居住者であっても日本で課税対象となることがあります。この点は「実態ベース」で判断されるため、税務署との見解のずれが生じやすい点に注意が必要です。
非居住者として活動する際は、「どの所得が日本で課税対象になるのか」を契約内容や支払い方法まで含めて明確にし、必要に応じて税理士や専門家に相談するのが現実的です。
フリーランス/法人の実務の違い
海外で収入を得る場合でも、個人事業(フリーランス)か法人かによって、税務実務は大きく異なります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
フリーランス(個人事業)
居住者であれば、海外取引を含めたすべての所得を日本で確定申告します。報酬を受け取った日付や為替レートの管理、経費計上の明確化など、自分で記帳・計算を行う必要があります。
非居住者になった場合は、日本国内で発生した報酬のみが課税対象になります。ただし、日本のクライアントとの取引で源泉徴収された場合、それが確定課税とみなされ、原則として確定申告の必要はありません(※還付申告等を除く)。
法人(会社設立)
法人を設立している場合は、たとえ代表者が海外を拠点にしていても、法人の「所在地」が日本にあれば、その法人は日本の税法に従って申告義務があります。
法人化のメリットは、個人に比べて経費の幅が広くなる点や、社会的な信頼を得やすい点などが挙げられます。一方で、記帳義務・決算・法人税申告・社会保険手続きなどの実務負担は大きくなります。
フリーランス・法人いずれの形であっても、海外収入を扱う場合は為替・源泉・居住地などの要素が絡み、判断が複雑になる場面が少なくありません。制度を正しく理解し、自分の働き方に合った形で運用することが大切です。
よくあるトラブルとグレーゾーンに注意
非居住者や海外収入に関する制度は、一見シンプルに見えても、実際にはグレーゾーンや落とし穴が多く存在します。制度上は正しい手続きを踏んでいるつもりでも、実務で思わぬトラブルに発展するケースは少なくありません。
ここでは、実際によくある誤解やトラブルの例と、それを避けるために意識しておきたいポイントを紹介します。
よくある税務・制度上のトラブル
- 住民票を抜いただけで非居住者になったつもりが、税務署に「居住者」と判断され追徴課税
- 海外から日本の報酬を受け取っていたが、源泉徴収されず、後から申告漏れとして指摘された
- 非居住者前提で社会保険を外したが、法人代表であることを理由に保険料を請求された
こうしたトラブルは、「これくらいは大丈夫だろう」という判断のズレから生じることが多く、後から修正や追納が必要になるケースもあります。
情報の真偽とリスクの見極め方
最近ではSNSやブログで「非居住者になれば税金ゼロ」といった話が広く拡散されていますが、それぞれの発信には背景や前提条件があるため、そのまま鵜呑みにするのは危険です。
- 法人を持たないケースと法人代表では社会保険の扱いが異なる
- 単発の節税体験談は再現性が低いこともある
- 実態が日本にあれば、形式上非居住者でも否認されることがある
判断に迷うときは、税理士への相談や税務署への事前確認を行うなど、事実ベースでの確認と、自己責任での判断が欠かせません。
実体験から見る判断のリアル|私は「居住者」を選びました
制度や実務の概要を踏まえたうえで、ここからは私自身の判断と体験をお伝えします。
非居住者になれば住民税や社会保険料が不要になり、所得税の課税範囲も狭まるなど、制度上のメリットは明らかに存在します。実際、節税や柔軟な働き方を求めて、非居住者という選択を取る人も増えています。
私自身も、ノマド生活を送るなかで、その選択肢について真剣に考えたことがありました。ただ私は、「日本の居住者」のままでいるという選択をしています。それは、節税よりも自分にとっての心地よさを大切にしたいと考えたからです。
このセクションでは、私が非居住者化を検討した経緯と、今の立場を選んだ理由についてお伝えします。
非居住者になるのが当然な人もいる
まず前提として、非居住者になること自体を否定するつもりはありません。
むしろ、海外に生活の拠点を移した人や、企業の辞令で長期駐在している人などは、制度上「非居住者」として扱うのが当然であり、それは選択ではなく原則です。
実務的にも、日本の居住者として手続きを継続するのは非現実的で、非居住者として処理されることこそが制度の趣旨に沿った形です。
問題は、私のように拠点を固定せず、長期間にわたって国をまたぎながら生活する、いわば「グレーゾーン」にいる人間です。
制度的には居住者か非居住者か、いずれかを選ばなくてはなりませんが、ノマド生活のようなスタイルは、そのどちらにも完全には当てはまりません。
損得では割り切れなかった理由
旅をしながら働くようになってから、「住民票を抜けば負担を減らせるのでは?」と考えたことは何度もあります。ネット上でも、非居住者になることで税金や保険料を抑えたという体験談は多く見かけますし、それが理にかなった選択肢であることも理解できます。
でも、私は最後までその道を選びませんでした。理由は、損得よりも感情のほうが大きかったからです。
これまで私は、教育や医療、そして日々の暮らしのあちこちで、日本という社会にずいぶん助けられてきました。
それは、自分の親や周囲の大人たちが、日々働いて税金を納めてくれていたからこそ、受けられていたサービスだったんだと思います。そうやって誰かが負担してくれていたからこそ、私は安心して育つことができた。そうした実感があります。
だからこそ、いま自由に旅を続けられるようになった自分が、「得だから」という理由だけでその繋がりを手放すのは、どこかで自分にうしろめたさを抱えたまま生きることになりそうだと感じました。
現実的にも「居住者」が合っていた
感情面だけでなく、現実的にも私は非居住者に向いていませんでした。
そもそも私は、そこまで高額の収入があるわけではありません。住所不定のノマドとして、税務上のグレーな立場に置かれたり、手続きをめぐってトラブルになるほうが、よほどストレスです。
それなら、適度に税金を納めながら、日本で年に数回の手続きをこなす生活のほうが健全で、自分には合っていると判断しました。
誰に見張られているわけでもありませんし、国に忠誠を誓っているつもりもありません。
でも、自分が受けてきたものを思うと、「もう少しだけ返してからこのまま旅を続ける」というほうが自然体でいられます。
旅人としての自由と、人としてのけじめ。その間で心地よい落とし所を探した結果、私は『居住者のまま』という選択に自然と落ち着いたのです。
居住者として旅を続ける現実
私は今、日本に法人を持ち、社会保険に加入し、申告と納税を行いながら旅を続けています。税に関する手続きは少し面倒に感じることもあります。一方で、クレジットカードや銀行口座、証券口座の管理などを含めて、「居住者」の方がいろいろとスムーズなのも事実です。
もちろん、非居住者のように税負担を最小限にする生き方を見て「うらやましい」と思うことがないわけではありません。でも、そこに至るまでの準備やリスク、価値観の違いを考えると、私は私なりのやり方でちょうどいいと感じています。
まとめ|自由に働くための税との向き合い方
海外を旅しながら働くノマドやフリーランスにとって、税金や社会保険との付き合い方は「避けて通れない現実」です。
非居住者という選択には合理的なメリットがある一方で、実態とのギャップやグレーゾーンによるリスクも存在します。そして、制度上の最適解がそのまま自分にとって幸せな選択とは限りません。
私は自分自身の価値観と照らし合わせた結果、「居住者」という立場を選びました。それは、制度に従っているからというより、自分がどう生きたいかという感覚の延長線にあります。
自分のライフスタイルや考え方に沿って、納得できる判断をすることが、自由な働き方を続ける上でいちばん大切なのだと思います。