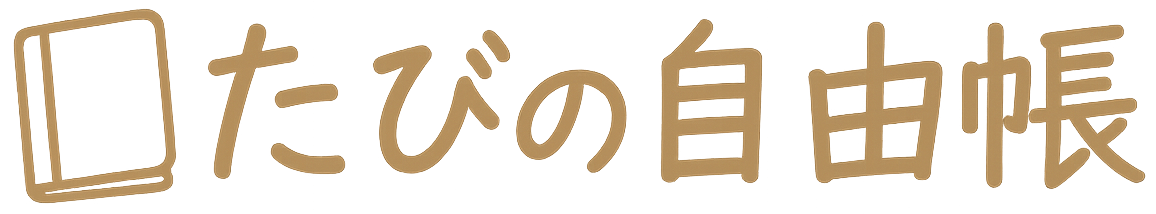旅をしていると、「これ、日本にあったら喜ばれるかも」と感じる出会いがたまにあります。
市場で見つけた素材や、現地の人とのやり取り。その一つひとつが、やがて商品になり、誰かの暮らしをちょっと豊かにする。
私はこのスタイルを本格的に仕事として取り組むようになりました。
現在は、海外で原料を仕入れ、日本のOEM業者と連携して製品化し、旅を続けながらECで販売しています。扱っているのは数種類の商品だけですが、仕入れ先とは継続的にやり取りをし、品質や納期なども細かく調整しています。
一見すると「自由なノマドワーカー」のように見えるかもしれませんが、実際には「個人で運営する小さな商社」のような働き方です。現地の生産者と信頼関係を築き、お客様に満足してもらえる商品を丁寧に届ける。そして、自分自身も旅を続けながら持続可能な収入を得る。そんな三者が無理なく幸せになれるビジネスモデルを、少しずつ形にしてきました。
この記事では、私自身の実体験をもとに、海外仕入れとEC販売を組み合わせた働き方の全体像、始め方、継続のコツをお伝えします。
旅しながら回せる「個人商社モデル」の全体像
海外で見つけた素材を仕入れ、日本で製品化し、ネットで販売する。言葉にするとシンプルですが、実際には、仕入れ、製造、販売、在庫、発送、顧客対応までを全部マネジメントする必要があります。まさに「個人で動かす小さな商社」といった感覚です。
この働き方を軌道に乗せるには、ただ商品を選んで売るだけでは不十分です。現地の仕入れ先と信頼関係を築き、OEM業者とのスケジュールや仕様をすり合わせ、商品が手元に届くまでの物流を設計する。そして、販売チャネルを選び、在庫と発送の体制を整え、購入者への対応も滞りなく行う。それらをすべて旅をしながら回していくには、綿密な準備と仕組みづくりが不可欠です。
私自身、最初はインスピレーションから始まりましたが、旅をしながら安定して販売を続けるためには、予想以上に綿密な計画と行動が必要でした。この記事では、以下のセクションでその全体像を順に分解していきます。
海外での仕入れと国内での加工・販売の流れ
私の場合、旅先で見つけた素材やアイデアがすべての始まりです。現地の市場で気になった素材を手に取り、品質や扱いやすさ、そして輸入可否までを確認します。その上で、日本で連携しているOEM業者と相談し、製品として成立させていく流れになります。
製品化にあたっては、デザインやロゴ、パッケージだけでなく、どのような用途で使ってもらうか、誰に届けたいのかまでを想定して仕様を固めていきます。OEM業者とのやりとりでは、試作・納期・ロットの調整があり、スケジュールに合わせた進行管理が必要です。
この一連の流れの中で大切にしているのは、「現地の仕入れ先」「製造を請け負う国内業者」「最終的に商品を受け取るお客様」、その全員が納得し、満足できる形に整えることです。安く仕入れて高く売る、という考え方ではなく、関わるすべての人に価値がある状態をつくる。
それが、私がこの仕事を長く続けられている理由だと感じています。
EC販売の主な方法と特徴
製品が完成したら、次は「どこで、どうやって売るか」を決める段階です。私が主に活用しているのは、自社EC(BASEやShopifyなど)とAmazonの併用です。メルカリのようなCtoCプラットフォームを使う人もいますが、私はある程度ブランドの世界観を伝えたいという思いがあるため、自社ECを軸にしています。
自社ECは自由度が高く、商品の魅力や背景を丁寧に伝えられる反面、集客や運営はすべて自分で行う必要があります。一方、Amazonのようなモール型は強力な集客力がある分、手数料や規約面の制約も多くなります。ただし、FBA(フルフィルメント by Amazon)を活用すれば、倉庫・発送・カスタマー対応をAmazonが代行してくれるため、旅をしながらでもほとんどの業務を手放せるというメリットがあります。
どのチャネルが正解かは、売りたい商品や目指すスタイルによって異なります。重要なのは、「売れそうな場所に出す」だけではなく、「誰に、どんな気持ちで届けたいのか」を軸にチャネルを選ぶことです。私は、商品を届けるという行為そのものが、自分と誰かをつなぐ仕事だと考えています。
始める前に準備すべきこと
旅をしながら物販を続けるには、偶然の出会いだけではなく、再現性のある「仕組み」が必要です。
思いつきでスタートしても、途中で壁にぶつかり、続かなくなるケースは少なくありません。だからこそ、最初にしっかりと準備を整え、「自分が不在でも回るビジネスモデル」を構築することが重要になります。
この章では、実際に私が準備してきたことの中から、特に重要だと感じた4つのポイントを紹介します。
ECチャネルの選び方と立ち上げの流れ
まずは「どこで売るか」を決めることから始まります。BASEやShopifyといった自社ECは、自由度が高くデザインや商品説明もこだわれます。ブランディングを意識するなら、自社サイトは非常に有効です。ただし、集客は自分で行う必要があるため、SNSやブログ、広告運用といった導線の設計が欠かせません。
一方、Amazonや楽天といったモール型のプラットフォームは、集客力が高く、短期間で売上を立てやすい反面、価格競争や手数料の高さ、規約の制約があります。どちらが優れているかではなく、自分の販売スタイルと顧客に合ったチャネルを選ぶことが大切です。
また実際には複数のチャネルを使い分ける事業者が多いです。自社ECでブランドの世界観を伝えつつ、Amazonで利便性を提供する、という使い分けも十分現実的です。私も実際に複数チャネルを組み合わせて運営しており、それぞれのメリットを活かすようにしています。
OEM業者との協業と信頼構築
製品化を進める上で欠かせないのが、OEM(受託製造)業者の存在です。私は現在、国内の決まった業者と継続的に取引していますが、最初にその業者を選ぶまでには慎重に時間をかけました。価格だけでなく、試作品の精度、対応の丁寧さ、納期管理、そしてこちらの意図をきちんとくみ取ってくれるかどうか、いくつもの視点で比較・検討しました。
実際には、Webで探した候補先に対してメールで問い合わせをし、いくつかの業者とオンラインや対面で打ち合わせを重ねました。最終的には、自分が実際に工場を訪れて、担当者としっかり話をしながら、信頼できる企業を選びました。
OEMとの関係では、仕様変更や製品化後の微調整といった細かい対応も多く発生します。試作段階から「完成形をどうするか」だけでなく、「何を大切に届けたいのか」を共有することで、より良い製品に仕上がっていきます。
価格や納期の交渉だけでなく、「お客様に責任が持てるものをつくれるか」という目線でOEMを選ぶことが、長く続けるための土台になると私は考えています。
海外仕入れ先との協業と信頼構築
私は多品種を短期的に仕入れるようなスタイルではなく、信頼できる現地企業と継続的にやり取りをしながら、限られた数種類の素材や原料を扱っています。取引を始める前の段階で「この相手と長く付き合えるかどうか」という視点をもつことが重要です。実際に対面で話しあって、これから一緒にビジネスをするパートナーとして信用できる相手かどうかを見極めます。
いざはじめると仕様確認はもちろんのこと、輸出の可否、必要な書類の取得、梱包の形態、輸送方法、品質管理体制など、細かな点まで徹底的に擦り合わせました。お互いの文化や言語の違いによる認識のズレを避けるため、仕様は写真付きで共有し、重要なやり取りはすべて記録を残すようにしています。
この関係が確立できると、2回目以降のやり取りは格段にスムーズになります。価格だけで選んだ一時的な仕入れ先ではなく、「一緒に商品を育てていくパートナー」として正面から向き合うことが、結果的に事業全体の安定につながると感じています。
仕入れ先との信頼関係を築くことは、商品そのものの品質だけでなく、お客様に安心して届けられる体制をつくるうえでも不可欠なステップです。
輸入と販売に必要な法的知識
輸入物販を始めるにあたって、法律や制度についてある程度の知識を持っておくことは避けて通れません。知らずに始めてしまうと、通関で止められて商品が廃棄されてしまったり、販売後に法的トラブルにつながったりするリスクがあります。
たとえば、食品や化粧品を扱う場合には、それぞれに応じた許可や表示義務がありますし、電化製品にはPSEマークの取得が求められます。輸入品に万一の事故があった場合に備えて、PL保険(生産物賠償責任保険)への加入も強く推奨されます。
また、個人利用と商用輸入では通関や関税の扱いがまったく異なります。私自身、最初は「とりあえず仕入れてみよう」という感覚で始めかけましたが、事業としてしっかりやっていくには、輸入ルールや必要な届出について真剣に学ぶ必要がありました。
今でも輸入前に必ず仕入れ先とすべての内容を確認し、必要に応じて国内の関連機関に事前相談したうえで、問題のない状態で輸入を行っています。万が一にも通関で止まれば、商品代金も送料もすべて無駄になります。
お客様に届ける商品である以上、「売る側としての責任」を持って対応することがとても大切だと感じています。
長く続けるための運営のコツと課題
旅をしながら物販ビジネスを続ける、その響きは魅力的ですが、実際には「始めること」よりも「続けること」のほうがはるかに難しいと感じています。
出荷の手配、顧客対応、商品改良、売上の波…あらゆる要素を自分でマネジメントするには、工夫と覚悟が必要です。
このセクションでは、私自身が試行錯誤してきた運営の実態や、つまずいたポイント、外注化や仕組み化で乗り越えた工夫を共有します。旅と仕事を両立させるには、どこまでを自分で担い、どこからを仕組みに任せるかという視点がとても重要になります。
在庫管理と発送の現実的な仕組み
「自分の手を離れても回る仕組み」を整えるなかで最も重要なのが、在庫と発送の体制づくりです。
日本国内の倉庫業者と提携すれば、商品が完成したらすべての在庫をその倉庫に納品し、注文が入ると自動で倉庫がピッキング・梱包・発送を行ってくれるため、アフリカにいようが南米にいようが、販売を止める必要がありません。
倉庫サービスの利用が難しい場合でも、家族や知人に発送を手伝ってもらったり、AmazonのFBA(フルフィルメント by Amazon)のような外部サービスを利用することも可能です。大事なのは、「海外から自分で発送する」という選択肢を最初から捨てることです。
毎日の発送業務を自動化できると、旅中の行動にも大きな自由が生まれます。Wi-Fi環境があるところで必要な時に必要な業務を行えばよくなり、まさに「仕組みで回すビジネス」が実現できます。
EC運営の効率化と外注活用
EC販売は一見「仕組みで回る」ように見えても、実際には日々の運用作業が多く、すべてを自分ひとりでこなすのは現実的ではありません。だからこそ、最初から「外注できる部分は外注する」という前提で考えることが重要です。
たとえば、私はWeb制作やマーケティングは自分でできますが、写真撮影やデザインなどビジュアル面は得意ではないため、一部の作業を信頼できるフリーランスに依頼しています。実際に自分の手でやるのは、売上管理や問い合わせ対応など、最小限に絞り込んでいます。
「全部を完璧に自分でやらなきゃ」と思うと、すぐに限界が来ます。むしろ、「自分にしかできないこと」に集中し、それ以外を外注化・自動化することが、長く安定して運営を続けるためのカギだと感じています。
信頼を支える「自分でやる仕事」の見極め方
外注化や自動化は確かに運営の効率を上げてくれますが、「何を自分でやるか」という判断はもっと大切です。特に、OEM企業とのやり取りや、海外の仕入れ先との調整、そして顧客対応といった「信頼を土台とする業務」は、今でも私自身が直接対応しています。
こうした部分を雑に扱うと、商品クオリティや納期のズレ、顧客満足度の低下といった形で、すぐにトラブルとして跳ね返ってきます。むしろ、ここにしっかり時間と手間をかけることで、事業の安定性が格段に増し、口コミやリピートといった形で成果として返ってくる実感があります。
「どこまでを仕組みに任せ、どこからを自分が担うか」、その境界線を意識的に引くことが、旅を続けながらも信頼されるビジネスを築く鍵だと思っています。商品の品質に直接的に関わる部分は一切の妥協をせず、そして実際に利用するお客様の声を聴き続けることで、本当に必要とされている商品を自信をもって提供し続けることができます。
まとめ|旅の感性を「商品」に変える働き方
「海外仕入れ × EC販売」という働き方は、単なる収入手段ではなく、旅で得た感性や気づきを価値に変える手段でもあります。現地での体験や発見が、そのまま商品やブランドのストーリーとなり、誰かに届く。それは、旅人にしかできない独自の価値創造です。
もちろん、仕入れやOEM連携、法律対応、販売チャネルの整備など、ビジネスとして成立させるためには多くの準備と継続的な運用が求められます。仕組み化・効率化だけでなく、「ここは自分で責任を持つ」という信頼ベースの判断も不可欠です。
それでも、ひとつひとつ積み上げていけば、「旅をしながら事業を続ける」というライフスタイルは確実に実現可能です。私自身、ゼロから始めてここまで続けてこられたのは、行動しながら試行錯誤してきたからだと思っています。
自分の感性と経験を信じて動けば、旅と仕事は対立するものではなく、むしろ相互に高め合えるものになる。そんな選択肢のひとつとして、この記事が誰かの背中を押せたなら嬉しいです。