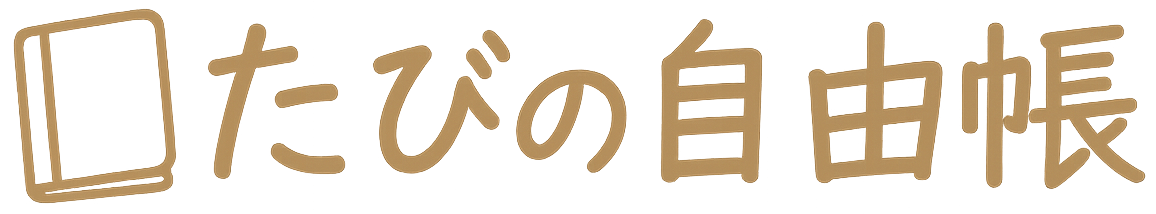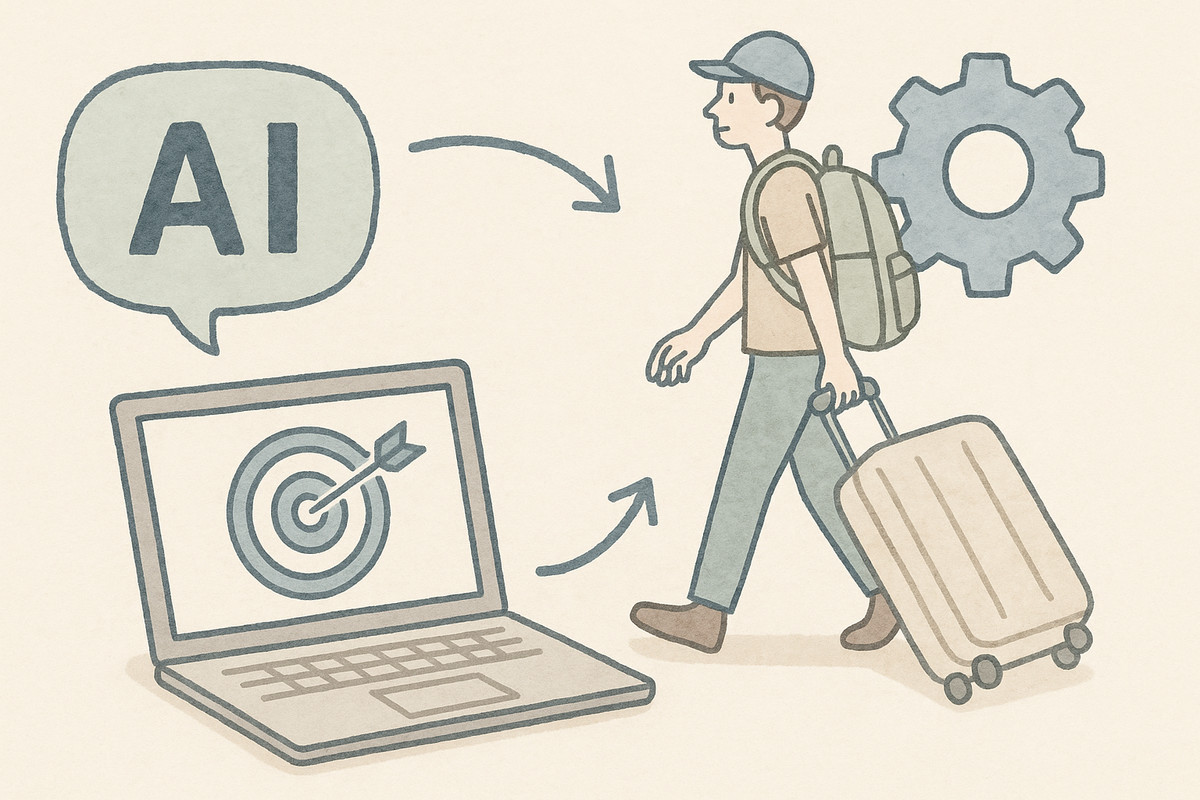旅をしながら働く。
そんな自由なライフスタイルを実現するには、「場所にとらわれずに収入を得られるスキル」が欠かせません。
私自身、会社員時代に財務・会計・海外事業の仕事をしていましたが、ゼロからWeb制作やマーケティングなどを学び、現在は複数のスキルを活かして旅と仕事を両立する働き方にシフトしました。
しかし近年、ChatGPTなどのAIの進化によって「せっかく身につけたスキルがすぐに時代遅れになるのでは?」という不安を感じる人も増えています。
現在の状況下では「どんなスキルがAI時代にも活きるか」を見極める視点も大切です。
この記事では、AIと共存しながら価値を発揮できるスキルの考え方や、旅と相性の良い仕事、自由な働き方へのステップを、私の実体験を交えて紹介します。
AI時代におけるスキル選び
AIの発展により、仕事のあり方は大きく変わりつつあります。スキルを選ぶうえで「AIに代替されないか」は無視できない視点となりました。
将来性のあるスキルとは、「AIにできないこと」だけでなく、「AIを活かしてより高い価値を提供できる分野」も含まれます。
(ここでいう将来というのは3年~5年先くらいまでの話であり、直近のAIの進化を目の当たりにすると、10年先にAIができないことをいま考えるのは難しいです。)
このセクションでは、スキル選びにおける重要な判断軸と、AIと共存しながら働くための考え方について、私自身の経験も交えながら解説していきます。
AIの進化により、単純作業やルーティン業務は急速に自動化が進んでいます。だからこそ今、選ぶべきスキルには「人間ならではの強み」が求められています。ここでは、AI時代でも価値が落ちにくいスキルを見極める3つの視点を紹介します。
AIを前提にスキルを活かせるかどうか
動画編集やWEBライティングのように、AIツールを使えば大幅に効率化できる分野もあります。
これからの時代は、AIを敵に回すのではなく、活かしながら価値を高めていくスキルの活かし方が重要です。
たとえば、AIで自動生成された記事を校正・補強・編集し、読者のニーズに合わせたコンテンツとして最適化する仕事など、AIツールを使いこなせること自体が強みになります。
文脈理解と人ならではの気遣い
現状のAIは、言語を流暢に操れるようになってきたとはいえ、「依頼者の背景をくみ取る」「ニュアンスの違いを読み解く」といった文脈理解には限界があります。
ライターなら「クライアントの意図を汲んだ表現」、動画編集者なら「視聴者の心を動かす構成」、Web制作者なら「ターゲットに合わせた導線設計」など、伝え方や目的達成の設計を担う力は、まだまだ人間のほうが得意な分野です。
応用力や総合力が問われるかどうか
単一の作業に閉じたスキルはAIに代替されやすい一方で、「複数スキルを組み合わせる」「状況に応じて柔軟に対応する」といった応用力や総合力が求められるスキルは、現時点ではAIにとってハードルが高いままです。
たとえば動画編集でも、「構成案+編集+SNS連携施策までまとめてクライアントの売り上げに直結する動画を提案できる」ような仕事は、クライアントにとっての価値が段違いです。こうしたスキルの掛け算と顧客の視点をもつ働き方こそ、AIに代替されにくい要素だといえます。
クライアントにとって「何を依頼すればいいのかわからないけど、この人に聞けば何とかしてくれる」という存在になれることが、継続的な信頼につながっていきます。
旅と相性がいいスキル系の仕事【実例一覧】
ここからは、実際に私自身が身につけてきたスキルや、周りの友人が実践していたスキル系の仕事を紹介します。
「どんなスキルがあれば、旅と仕事の両立ができるのか?」という疑問に対して、具体的な働き方のイメージが湧くような構成にしています。
いずれも、オンラインで完結できる・業務の自由度が高い・仕事の幅が広いという3つの特徴を持っています。
Web制作(HTML・CSS・JS・WordPress)
私が最初に学んだスキルのひとつがWeb制作です。HTMLとCSSの基本から始め、WordPressの構築やカスタマイズができるようになることで、個人サイトや企業ページの制作案件を受けられるようになりました。
Web制作の魅力は、「成果物が目に見える形で残る」ことと、「仕事の幅が広い」ことです。シンプルなブログサイトから、企業のLPやコーポレートサイト、海外向けの多言語サイトまで、ニーズは非常に多様です。
WordPressは、世界中で使われているCMSであり、習得しておくとフリーランス案件だけでなく、自分自身のブログやサービス展開にも活かせます。私も今この旅ブログを自作しています。
旅との相性
- 作業はすべてPC上で完結。ネット環境が安定していればどこでも対応可能
- 長期案件が多く、旅のペースに合わせてスケジュール調整しやすい
- チームでの開発に参加する場合、時差ややり取りの柔軟性が求められることも
学習と仕事の獲得方法
- ProgateやドットインストールなどでHTML/CSSの基礎を習得
- WordPressやそのカスタマイズを学び、自作サイトを1つ作る
- クラウドソーシングで簡単な修正案件から実務経験を積む
AI時代の視点
現時点では、コードの補完やテンプレート生成はAIが得意とする部分です。しかし、クライアントの意図をくみ取って、実際のビジネスに合う構成を提案することや、ちょっとしたデザイン調整などは人の感覚が必要とされる領域。
また、状況に応じて細かな知識と経験がものを言う場面では、AIを活用しつつ人間の介在価値を発揮する余地が大きいといえます。
Webライティング
旅中でも比較的すぐに始められるスキルの一つが、Webライティングです。私自身も最初期に実務を経験した分野であり、のちにSEOなどを学んで、以降もクライアントのコンテンツ制作をサポートしてきました。
Webライティングは「文章を書けるかどうか」ではなく、「読者の悩みを理解し、それに応える文章が書けるか」が問われる仕事です。SEO(検索エンジン最適化)の視点を取り入れたり、集客や売上に貢献するライティングへと進化させるなど応用範囲の広い仕事です。
旅との相性
- 書く作業は場所を選ばないため、どこでも作業できる
- ネット回線が不安定でも、オフラインで下書き→後で投稿が可能
- 時差のある国でも納期管理さえできれば仕事に支障なし
学習と仕事の獲得方法
- 基礎知識(検索意図、構成、読者ニーズなど)を学習
- 自分のブログやnoteなどで文章を発信し、反応を見ながら改善
- クラウドソーシングで「記事作成」の案件にチャレンジ
- 慣れてきたら構成作成や編集、ディレクション業務にステップアップ
文章力だけでなく、情報収集力などの感度も磨かれていきます。旅をしながら文章を書くことは、自身の体験をそのまま価値に変えられるという点でも魅力的です。私の場合、もともと業務としてやっていたライティングが、現在はこの旅ブログの執筆に活かされています。
AI時代の視点
AIライティングツールが進化している今、「ただの文章生成」はすでに代替可能な時代です。
しかし、記事の狙いを理解し、SEOであれば検索意図に合った構成を設計し、適切な情報や事例を読者ニーズに合わせて取捨選択する力は、現状では人間のほうが優れています。また、AIの文章をチェック・リライトして編集する力も重宝されるようになっています。
記事の企画や監修、ユーザー目線での改善提案ができるライターは、AI時代でも活躍の場を広げられる分野といえるでしょう。
動画編集/ショート動画制作
旅と相性の良いクリエイティブなスキルのひとつが、動画編集です。特に最近はYouTubeやInstagram、TikTokなどのSNS向けに、短尺の動画(ショート動画)を求める案件が増えており、初心者でも入りやすくなっています。
旅をしながら映像を作るスタイルは魅力的ですが、長時間の編集の場合はなかなか煩雑さもあるため、自分の作業スタイルとの相性を見極めることが大切です。
旅との相性
- 編集作業はPCで完結。ただし、内容によってはそれなりのPCスペックが必要
- 納品動画の尺が短ければ、ネット回線が弱くてもアップロード対応可能
学習と仕事の獲得方法
- 無料・有料の編集ソフト(DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro, CapCutなど)で基礎を学習
- 自分の旅を題材に練習し、ポートフォリオを数本作る
- クラウドソーシングでSNS用動画やテロップ入れ、BGM編集の案件から始める
- 構成力やマーケティング視点を取り入れて単価アップを目指す
私自身はこの分野を学んだものの、フリーランスとしてこの分野で稼いだことはありません。自身の仕事の中での軽い編集程度ならしますが、クライアントワークとして高いレベルの作業が必要なときはフリーランスの仲間や外部に委託します。
AI時代の視点
動画編集はAIの進化によって自動化が進んでいる分野でもあります。特にカット編集やテロップ挿入などの単純作業は、AIやテンプレート機能で大幅に効率化が可能です。
その一方で、
- 構成の意図を読み取る力
- 企画段階から提案できる編集者
- ブランドの世界観に沿った表現のコントロール
といった人の感性や判断が求められる部分は、今も人間が優位です。
単純作業だけでなく、クリエイティブ寄りのスキルやマーケティング視点での提案力を磨くことで、AIと差別化できる編集者になることが可能です。
デザイン
バナー制作やSNS投稿画像、Webサイトのビジュアル設計など、グラフィックデザインは旅先でもできる代表的なスキルのひとつです。特にCanvaやFigmaなど、クラウドベースのツールが登場してからは、環境さえ整えばPCひとつでどこでも仕事が可能になりました。
デザインは「自分の美的感覚が活かせる」分野ではありますが、それだけでは成り立ちません。目的に沿った設計と、クライアントとの意思疎通が肝になります。自己表現としてのデザインとクライアントワークとしてのデザインは別物になりがちです。どちらの道に進むにしても基本的なスキルは共通します。
旅との相性
- PCさえあれば世界中どこでも作業可能
- オンラインツールでの共同作業も進めやすい
- データ容量が軽めなため、納品や共有もスムーズ
学習と仕事の獲得方法
- CanvaやFigmaで操作を覚え、テンプレートを活用して練習
- バナー・SNS画像などの制作を繰り返し、ポートフォリオを作成
- クラウドソーシングで「画像修正」「チラシ作成」などの小規模案件に挑戦
- クライアントワークに移行する際は、ヒアリング力や要件整理も重要
私自身もこの分野を学びましたが、視覚的な表現が得意とは言えず、実務のほとんどは他のフリーランスに委託しています。簡単な画像の編集は自分でしますが、より高いレベルの技術が必要な場合は他のプロに任せています。デザインスキルは幅広い分野で応用が利くので、学んで損はない分野だと感じています。
AI時代の視点
デザイン分野でも、AI画像生成(Midjourney、Canva AI、Adobe Fireflyなど)の進化により、ビジュアル制作が急速に変化しています。
ただし、
- クライアントの意図を深くヒアリングし、課題解決に導く力
- 細かいレイアウト調整や、ブランドトーンへの整合性
- 全体構成を設計できるスキル(UI/UXなど)
といった部分では、人間の判断や文脈理解が欠かせません。
「装飾」ではなく「目的達成のための設計」という視点でデザインを扱える人材は、今後も高いニーズがあります。
SNS運用(代行・企画・投稿管理)
企業や個人のSNSアカウントを代行運用する仕事は、パソコンやスマホひとつで完結しやすく、旅との相性も良い副業のひとつです。投稿内容の企画やスケジュール管理、簡単な画像編集、コメント返信などが主な業務で、作業の再現性も高いため、未経験から始めやすい分野でもあります。
SNS運用はシンプルに見えて、「相手の伝えたいことを理解し、読者の目線で表現する力」が求められます。私は自分では運用しないものの、マーケティング業務のなかでSNS業務を請け負う際には、全体のコンセプト設計やKPI設計をサポートする役割を担っています。
旅との相性
- 投稿作業やスケジュール管理はすべてオンラインで可能
- 時差のある地域でも、予約投稿ツールを使えば対応できる
- 長時間の集中作業が少ないため、短時間で完結しやすい
学習と仕事の獲得方法
- 自分のSNSアカウントで発信を試し、基本的な運用スキルを体得
- Canvaなどを使った投稿画像作成、アナリティクス分析の練習
- 小規模なアカウント運用を請け負い、PDCAを回しながら改善提案
- ゆくゆくは企画・戦略まで含めた提案ができると、単価が上がる
私自身はSNS自体があまり好きではないため、実務として対応することはありません。ただし、マーケティング全体の中でのSNS設計や投稿方針のディレクションなどを担当することはあります。
AI時代の視点
AIツールの進化により、SNS投稿文の自動生成、ハッシュタグ選定、画像生成などは一部自動化が進んでいます。しかし、
- フォロワーの反応を踏まえた改善提案
- ブランドに合ったトンマナの維持
- 継続的なファン育成やエンゲージメントの構築
といった運用の本質は、依然として人間の判断が重視されます。
「手を動かす作業」から「ブランドを育てる視点」へのシフトが、AI時代のSNS運用には求められます。
プログラミング
プログラミングは、世界中どこにいても高単価案件を受けやすいスキルです。業務内容は幅広く、Webアプリの開発、業務ツールの自動化、既存コードの修正や保守などがあります。クラウドソーシングでも案件が多く、旅をしながらでも比較的安定した収入を得やすい分野です。
プログラミングは「学ぶコストは高いが、習得すれば強力な武器になる」スキルです。特に一人で完結できる作業が多く、技術的な信頼を得られれば単価も高くなります。
私自身も基本的なプログラミングスキルを学びましたが、現在は仕事としてプログラミングをすることはほぼありません。しかし、日常的な業務の中でプログラムを書いて効率化できるのは、他の分野の仕事においても非常に強いアドバンテージになっています。また、逆に自分の仕事で必要になるときは、海外のクラウドソーシングで外注しています。
旅との相性
- 案件ごとに開発環境(言語・フレームワーク・DBなど)を整える必要があるため、技術的な柔軟性と自己管理力が求められる。
- オフラインでもコード執筆や一部のテストは可能だが、Git操作や開発ツール(エディタ、Docker、ローカルサーバなど)の理解は必須。
- 納期やマイルストーンに合わせた進行が多く、プロジェクトベースでは時期によって忙しさに波がある。
学習と仕事の獲得方法
- HTML/CSS/JavaScriptなどのフロントエンドから学習を開始
- PythonやPHPでバックエンドの基礎も習得し、簡単なWebアプリを作成
- GitHubでコード管理を学び、ポートフォリオを公開
- 小規模な修正案件や機能追加などからスタートして、徐々に難易度を上げる
AI時代の視点
AIによるコード生成(例:GitHub Copilot、ChatGPTなど)は進化を続けていますが、
- 要件の抽出や全体設計、保守運用の視点は依然として人間が担うべき部分
- コードの品質やセキュリティ確保、技術選定などもAIだけには任せきれない領域
プログラミングスキル自体は「将来性があるかどうか」で一括りにできないため、AIとの棲み分けを意識した学習と実務経験の積み上げがカギになります。
そもそもAI自体がプログラムによって構築されているので、AI時代の必修知識と言っても過言ではないでしょう。
マーケティング支援(戦略・設計・統合スキル型)
マーケティング支援は、私が現在メインで行っている仕事です。Web制作・SEO・ライティング・分析・デザイン・広告運用など、複数のスキルを組み合わせてクライアントの課題を解決する「統合型の仕事」です。旅をしながらでも信頼関係を築ければ、継続案件として成り立ちます。
私自身、会社員時代に財務・会計・経営管理部門で働いた経験があります。その後、独学でデジタルスキルを習得し、複数スキルを統合して自営業者として活動を始めました。現在はプロジェクト単位でフリーランスに一部実務を委託しながら、自分は全体の設計やディレクションに集中しています。
旅との相性
- 業務の大半はオンライン完結だが、信頼関係の構築には時間が必要
- タイムゾーンがずれると会議・やり取りに支障が出る可能性あり
- 長期的な関係性・安定収入を得たい人には向いている
学習と仕事の獲得方法
- SEO、SNS、ライティング、デザイン、分析など基礎スキルを1つずつ習得
- 自分のメディアやSNSなどで実験・改善を繰り返し、成果を数字で説明できるようにする
- 小規模な相談対応や、プロジェクトの一部サポートから実績を積む
- 信頼されることで、戦略設計や上流の仕事を任されるようになる
マーケティング支援は、「ひとつのスキルだけでは届かない価値」を提供できる仕事です。全体を見渡し、課題を発見し、施策に落とし込む力が求められます。私はこの分野に最もやりがいを感じており、旅をしながらも高い信頼性を維持できるよう常に工夫を重ねています。
AI時代の視点
AIによる自動分析ツールや提案機能も進化しています。部分最適化に関する制度はかなり上がっているように感じますが、全体から判断してどの戦略を実行するかといった広い視点で判断する力はまだ人間のほうが高いと感じています。文脈で考えたり、逆にゼロベースで考えたり、広く見たり、局所集中したり。こうした問題定義がそもそも難しい分野においては、まだまだAIに勝てると私自身も自負しています。
今後はむしろAIで作業を効率化しつつ、戦略設計や全体調整に集中できる人材の価値はさらに高まるでしょう。
日本語教師(プラットフォーム型)
世界中の学習者にオンラインで日本語を教える「日本語教師」は、旅をしながらでも働ける選択肢のひとつです。なかでもItalkiやPreplyなどのプラットフォーム型サービスを活用すれば、集客や予約管理の手間を最小限に抑えつつ、スキマ時間で安定した収入を得ることが可能です。
私自身はこの仕事を実践していませんが、実際にプラットフォームに登録して日本語を教えている友人がいます。話を聞く中で、スケジュールを自分で調整できること、そしてネット環境さえあれば場所を問わず働ける点で、旅との相性は非常に良いと感じました。
旅との相性
- 自由にスケジュールを設定できるので、観光や移動と両立可能
- 1回30〜60分のレッスンで、空き時間を収入に変えやすい
- 移動の多い地域や時差の大きい国でも、柔軟に調整できる
学習と仕事の獲得方法
- プラットフォームに登録し、プロフィール・自己紹介動画を作成
- レッスン内容を組み立て、初心者向け/会話中心など自分の強みを明確化
- レビューと実績を積みながら、価格や指導スタイルを調整
- スキルや人気に応じて予約数・単価が上がっていく
旅の中で経験を積み、「もっと自由に働きたい」「ブランディング力に自信がついた」と感じたら、個人でのオンライン教室運営も選択肢になります。ただしこの場合、集客や教材制作、予約管理などもすべて自分で行う必要があるため、旅の最中にいきなり始めるには不向きです。まずはプラットフォーム型で基礎を固め、時間や余力に応じてステップアップを目指すのが現実的でしょう。
AI時代の視点
日本語教育そのものは、文法や発音などルールベースの部分が多く、AIとの親和性が高い分野です。ただし、
- 発音矯正や自然な会話のやり取り、文化的背景に基づいた指導などは人間の教師ならでは
- 生徒の反応を見て教え方を柔軟に変えるといったライブの対応力はAIには難しい
今後は「AI教材 × 人間教師」の併用スタイルが主流になる可能性が高く、AIを補助的に活用できる日本語教師は、むしろ求められる人材になるでしょう。
クラウド経理・記帳代行
クラウド会計ツール(freeeやマネーフォワードなど)を使って、個人事業主やフリーランスの経理業務をサポートする「クラウド経理・記帳代行」は、会計の知識を活かして旅をしながらでも可能な仕事のひとつです。
私自身は旅中にこの仕事をした経験はありませんが、税理士の友人が記帳代行業務を税理士業務の一環としてオンラインで行っていた例を知っています。在宅で完結し、やりとりもチャットベースで済むことが多いため、時間と場所に縛られにくい仕事として一定の可能性はあります。
旅との相性
- 時間帯の制約が少なく、納期さえ守れば対応できる
- 信頼関係と正確性が重視されるため、誠実な対応力が必須
- 会計の知識や実務経験がないと、参入障壁はやや高い
学習と仕事の獲得方法
- 会計知識(簿記2〜3級程度)があるとベースになりやすい
- クラウド会計ツールの操作に慣れ、サンプル業務などで練習
- クラウドソーシング(例:ココナラ・ランサーズ)や知人経由で案件獲得
- 継続案件に育てれば、旅中でも安定した収入源に
税務の判断が必要な場合は税理士資格が必要になるため、業務範囲は「記帳まで」にとどめるのが一般的です。
会計のバックグラウンドがある人には非常に相性がよい仕事ですが、ゼロから始める場合はスキル習得にやや時間がかかるため、スキル取得+実務訓練をセットで計画することが重要です。
AI時代の視点
記帳業務はAIとの競合が進んでいる分野です。しかし、すべての人が実際にAIで記帳するようになるまでには、だいぶ時間差があるように思います。また、現状ではまだまだAIだけでは完璧な記帳をすることはできません。AIでの記帳を前提にして、それをチェックできるような人材はこれからも必要になります。今後はAIを巧みに操り、記帳を効率化できる能力が求められるようになるでしょう。
翻訳・ローカライズ(語学スキルの実務活用)
語学力を活かした翻訳業務は、旅をしながら取り組みやすい仕事の一つです。
私自身もフリーランスになった初めのころにWEB記事を翻訳する案件を受けたことがあります。英語能力だけで勝負するよりも「翻訳+専門分野」など、複合的なスキルとして仕事を受けるほうが単価をあげやすいです。
旅との相性
- PCとネット環境があれば作業可能で、時差を活かせる案件も多い
- 納期ベースの仕事が多く、時間管理がしやすい
- 英語・スペイン語・フランス語など渡航先での語学習得とリンクしやすい
学習と仕事の獲得方法
- 一般的な翻訳は英語の読み書き+構文理解がベース
- 専門分野(法律・医療・ITなど)に強いと単価アップが見込める
- クラウドワークス、Gengo、Conyacなどプラットフォーム経由の受注が可能
AI時代の視点
自動翻訳(DeepL、Google翻訳など)の精度が向上している一方で、「読ませる文章」「マーケティング的な調整」「違和感のない日本語化」は依然として人の手が必要です。AI翻訳後の修正・編集の需要が増加しています。今後はAI翻訳を活かしつつ、文脈やターゲット文化への最適化で付加価値を出すのが鍵となります。翻訳は語学力だけでなく、「相手に伝わる表現力」や「専門知識」との掛け合わせが強みになります。
スキルをどう選ぶか?私が意識してきた5つの判断軸
私自身、スキルゼロから旅と仕事を両立する働き方に挑戦してきました。
その中で、スキルを選ぶときに意識していたのは、次の5つの視点です。
- 楽しめるかどうか
興味が持てないスキルは長続きしません。学ぶ過程も、続ける日々も、「やっていて面白い」と思える感覚が何よりの推進力になります。 - 旅との相性がいいか
ネット環境や作業時間、時差の影響など、自分の旅スタイルと両立できるか。現実的に無理なく続けられることが大前提です。 - 収入につながりやすいか
案件数、単価、継続性の3つは重要な判断軸。スキルを活かして実務経験が積みやすい分野は、自然と次につながります。 - 将来性があるか
学び続けることでどう展開していけるか。他スキルとの掛け合わせや、事業化の可能性が見えると、育てがいがあります。 - AIに代替されにくいか
AIと共存できるかは今後ますます重要になります。人の感覚、判断、文脈理解が必要な領域かどうかを見極めてきました。
どれも完璧に当てはまる必要はありません。
私も「まずは一歩踏み出してみる」ことから始まりました。経験を重ねながら、自分に合う働き方が見えてくるのだと思います。
スキルを仕事につなげる第一歩
スキルを学びながらでも、小さな仕事に挑戦することは可能です。実務の経験を積むことが、結果的にスキルの定着にもつながります。旅に出る前に副業として小さく始めておくのが理想ではありますが、出発後に実務をスタートさせたとしても、そこから着実に道を切り開くことはできます。
私自身、会社員時代にWeb制作を学び始めましたが、実際に初めて案件を受けたのは旅に出てからです。クラウドワークスで小さな依頼を受け、納品を重ねていく中で、ライティングやSEOなど別の分野にも挑戦するようになりました。徐々に仕事の幅が広がり、やがて複数のクライアントとの継続的な取引が生まれ、現在ではマーケティング支援を軸とした事業を展開しています。
SNSでの発信は必要か?
「ポートフォリオやSNSで発信しないと仕事が取れないのでは?」という不安を持つ人も多いですが、実際にはそうとは限りません。人には向き・不向きがあり、外向的に自分を売り出せる人もいれば、静かに実績を積み重ねていくほうが合う人もいます。
私は内向的な性格で、SNSやブログなどで発信することはしていませんでした。その代わり、受けた仕事一つひとつに丁寧に対応することで信頼を積み上げてきました。結果的に、納品物を見たクライアントから継続依頼や紹介が生まれ、事業が広がっていきました。
小さな実績が信頼につながる
最初の案件は単価が低くても、「実際に仕事として納品した経験」は大きなアドバンテージになります。プロフィールや提案文に書ける実績が一つ増えるだけでも、次の案件の獲得率は上がります。
たとえ旅の途中でスタートしても、実務を通じてスキルが磨かれ、信頼が得られるようになれば、自由な働き方は現実のものとなります。
信頼を築き、継続的な働き方へ
スキルを習得しても、それを仕事として継続させていくには、信頼されることが必要です。そして、信頼の最も確かな証が「次もお願いしたい」と言われること。つまり、指名される力です。
私の場合も、最初はクラウドワークスで受けた単発案件がスタートでしたが、納品後の丁寧な対応や、納期の厳守、提案の一言添えなど、当たり前のことを一つひとつ積み重ねることで、継続案件や紹介へとつながっていきました。
また、複数の案件を通じて自分の得意・不得意を把握できたことも大きなポイントです。得意な部分でしっかり成果を出すことが、相手の信頼を得る近道でした。
仕事の姿勢がポートフォリオ以上に重要
多くの人が「実績がないから仕事が取れない」と悩みますが、実はクライアントが見ているのは、成果物そのものだけではありません。納品までのやりとりや、納期管理、レスポンスの早さなど、仕事への姿勢も非常に重要です。
特に、旅をしながら働く場合、時差や通信環境の制約がある中でも「きちんとやり遂げてくれる人」と感じてもらえるかどうかが問われます。逆にいえば、どんな場所にいてもその信頼さえ得られれば、場所に縛られず仕事を続けることが可能になります。
継続や紹介が自由な働き方につながる
一つひとつの仕事を丁寧に対応することで、信頼が積み上がり、やがて営業をしなくても仕事が回るようになります。現在の私は、既存のクライアントとの長期契約以外の仕事は受け付けていません。
自由な働き方を持続可能なものにするには、「誰かに選ばれる存在」になることが欠かせません。その第一歩は、目の前の仕事に誠実に向き合うこと。それが一番の近道でした。
スキルの掛け算とチーム化|旅しながら事業化するという選択
スキルを一つ身につけるだけでも仕事の選択肢は広がりますが、複数のスキルを掛け合わせることで、その幅は一気に拡張します。Web制作にライティングやSEOを加える、動画編集にSNS運用や広告の知識を重ねる。こうした掛け合わせは、単なるスキルの足し算ではなく、クライアントからの信頼や単価に直結する「価値の掛け算」になります。
さらに業務が拡大していくと、一人で担える範囲には限界が生じます。そのとき、外部と連携してチームを組むことで、より大きな案件や長期的な関係構築が可能になります。私自身も、得意分野に集中しながら、苦手な領域は信頼できるフリーランスに外注する体制をつくってきました。
スキルを磨き、掛け合わせ、そして必要に応じて協業していく。このプロセスを積み重ねることで、旅をしながらでも持続可能で自由な働き方を築いていくことができます。
一つのスキルから掛け合わせるステップアップ
最初に学んだスキルを起点にして、実務を通じて次のスキルへと広げていく。それが、掛け合わせの第一歩です。私自身、Web制作を学んだあと、必要に応じてライティング、SEO、デザイン、プログラミングなどを追加で習得してきました。きっかけはすべて「この業務を自分でカバーできれば、もっと価値を出せるのでは」という実務現場での実感でした。
たとえば、単にWebサイトを作るだけでなく、集客戦略や検索順位を考慮した設計ができるようになると、クライアントからの信頼も一段と深まります。掛け合わせによって、依頼される仕事の幅も、単価も変わっていきます。
最終的に事業化・チーム化という働き方も
スキルの幅が広がると、ひとりで担える業務量にも限界が見えてきます。そこで必要になるのが「外部との連携」です。私もある時期から、特に苦手なデザインや動画編集などの分野は、信頼できる外部パートナーに依頼し、自分は全体の設計や戦略立案に集中するようにしました。
そうすることで、大きな案件にも対応できるようになり、クライアントとの関係性も「外注先」ではなく「事業パートナー」へと進化していきました。チームを組むことで、自分一人の能力以上の価値が提供できるようになります。
将来的なキャリアの選択肢を広げる
チーム化や役割分担が軌道に乗ってくると、自然と「次のステージ」が見えてきます。私の場合は、フリーランスという枠を越えて、業務の一部を法人化し、持続可能な事業としての基盤を築きました。これは、拡大を目的にしたわけではなく、自由な働き方をより安定させるための選択でした。
旅をしながら働くというライフスタイルの中でも、キャリアや収入の天井を設けず、必要に応じて柔軟に形を変えていける。そうした広がりを持つことで、楽しく働くことができると感じています。
まとめ|自力で価値を生み出す力こそ、最も本質的なスキル
スキルを学ぶことはスタートにすぎません。本当に価値があるのは、そのスキルを使って自分の力で価値を生み出し、収入につなげていけるようになること。単なる知識や技術だけでなく、それを現実の仕事につなげる力こそが、あらゆる時代を通じて通用する“再現性のある強さ”だと私は思っています。
私自身も、会社員として働きながらWeb制作を学び、旅に出てからライティングやSEO、マーケティングといったスキルを掛け合わせてきました。その過程で少しずつ「自力で稼ぐ力」が育ち、それがいまの自由な働き方の基盤になっています。
AIが当たり前になった今、スキルを持っているだけでは足りません。どう活かすか、どんなスタイルで仕事に落とし込めるかが問われています。重要なのは、AIに負けない能力を探すのではなく、AIと共存しながら成果を最大化できる人になること。そしてその第一歩は、「やってみたい」と思える分野に手を伸ばし、小さな実践を重ねていくことです。
旅をしながらでも、自分らしい働き方はつくれます。スキルを育て、それを使って価値を届けられるようになる過程そのものが、あなただけのキャリアになっていきます。